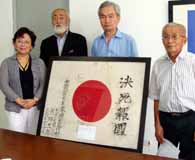65年前の恩讐を超えて=当事者日高が語るあの日=《6》=環太平洋を股にかけ=波乱万丈な父の生涯
ニッケイ新聞 2011年2月12日付け
日高徳一の祖父・末五良(すえごろう)は宮崎県の旧薩摩藩に属す地域の出身で1877(明治10)年に起きた西南の役の時、「〃一蔵(いちぞう、大久保利通の前名)を懲らしめないといかん〃と言って、見たことも声を聞いたこともない西郷どんのために出兵しました。貧乏士族、いや足軽だったと聞いている」と思い起こす。これは西郷隆盛を盟主に担ぎ上げ、明治初期の一連の士族反乱中、最大規模にして日本最後の内戦となった。明治の熱い血が滾った家系であった。
薩摩藩は身分の区別が厳しいことで知られ、明治維新ではそれに対する反発から万人平等の思想に共鳴する人、平民が大統領になれる米国の現実を一目見ようと飛び出す人が多くいた。
徳一の父・源三(げんぞう、宮崎)は1886(明治19)年生まれで、戦前にサンパウロ州新報を立ち上げた香山六郎(熊本)と同じ生年だ。香山は22歳にして笠戸丸で渡伯する機会をえたが、源三は早くも16歳にして上海に渡り、日露戦争をはさんで2年間ほど東亜同文書院(愛知大学の前身)で書生をしていた。海外に日本人が創立した最も古い学校の一つだ。その時、西欧列強にひしがれていたアジア諸国民の喜び様を目の当たりにしたに違いない。
その間にシンガポールでゴム園を経営する日本人元大佐に働かないかと誘われたこともあったが、当初から描いていた渡米の夢を捨てきれず、帰国して機会を虎視眈々と伺っていた。
29歳にして北米に命からがら密航した。「水が凍るように冷たい冬は海に飛び込んで密航する者がいないといわれていたので、わざわざ冬を選んで渡航し、船から飛び込んで密航したそうです」と父は徳一に語った。ポートランドに滞在したというから、カナダとの国境のバンクーバーから密航したようだ。
さらにはアラスカまで足を伸ばすなど波乱万丈な9年間を過ごすも、1924年に成立したアメリカ排日移民法が上下両院を通過、施行された。排日運動の激化により、源三は38歳の時やむを得ず帰国した。そしてマサと結婚、源三が40歳、マサが30歳の時に徳一が男3人兄弟の次男として生まれた。
「父は米国にいる間に第一次大戦だかシベリア出兵だかの召集令状が実家の方へ来て、密航中だったのでそれに行けんかった。そのことをいつも悔やんでいた。『日本人としての義務を果たしたかった』と何度も言っていた」と思い出す。外国で苦労した移民は、日本人であることの証を生きる支えにして日本精神を滋養すると言われる。
若くして海外志向の強かった源三にとって、夢を抱いて渡った米国で成立した排日法には絶望を覚えた。そんな生活の中で、命を賭してお国の為に尽すことは日本人としての務めであるとの気持ちが心中深く刻み込まれていたとして不思議はない。夢破れて帰った祖国でも厳しい現実が待っていた。年々不況が生活を圧迫し、海外渡航熱がさらに高まっていた。
源三は初めて家族を連れて〃3度目の正直〃のつもりで海外渡航に挑戦したのだろう。源三46歳、徳一6歳の時だった。1932年12月サントス着のもんてびでお丸で渡伯し、最初はモジアナ線の外人耕地に配耕され、2年コロノ生活をした後、新移民の常としてパウリスタ延長線の日本人植民地を転々とした。「両親はデカセギのつもりで5年したら金を貯めて帰るから学校なんか行かなくていいって、僕は日本語学校にすら行かなかった」。
ところがすぐ2年後、ブラジル版排日法である二分制限法が施行される。米国での悪夢の二の舞だった。しかも錦衣帰郷どころか帰りの旅費さえままならない現実・・・。環太平洋にまたがる激動の歴史に奔走された源三は、自分の果たせなかった夢を子供に託したに違いない。
源三は「日本人は世界で一番優秀な民族だ」と繰り返し子供に説き、そのような本ばかり読んで、二言目には日本精神の在り様を説いた。徳一は「オヤジが日本人としての考えをわし等の頭に突っ込んだのかもしれないが、実際に自分もそうだと思っていた。決してオヤジのせいだとは思わない」と言明する。(つづく、敬称略、深沢正雪記者)