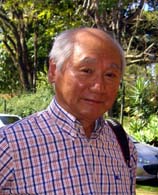南米産業開発青年隊55周年=夢の新天地を求めて=(中)=訓練所の思い出深い生活=NECなどに続々と就職
青年隊として正式に移住枠を取得し、訓練所での生活が始まったのは58年以降のことだった。第1期生から9期生までがウムアラーマの訓練所で約1年間の共同生活を営んだ。
国の事情を確かめ、気候風土に慣れ、言語や生活習慣を身に着けることが訓練所設置の名目。また建設技術者であっても、ブラジルの農業を身に付けることは将来的に有利とし、農作業も訓練の一部となった。
しかし元隊員らによれば「言語の習得もままならず、単なる自給自足の生活に過ぎなかった」と訓練とは名ばかりだったという。肝心の土木技術を身に着けたのも、実は日本だった。

58年に着伯した第1期生の本間健さん(78、山形)=ウマラーマ市=は、「訓練所に来た時は、先輩が作ってくれた寝泊りできる宿舎だけだった」と語る。
訓練所の宿舎といっても、広い部屋に二段ベッドを並べただけの簡素な宿舎だった。倉庫や車庫など付帯施設を建設し、自給自足の基盤づくりから始まった。
「1期生の主な任務は食糧作り。土地を開墾し稲を育てた。私は7期生の時代まで水田班の班長として基地に残った」。
やがて野菜、養豚、後にトラクターの運転や修理を担当する機械班などが誕生し、それぞれが分担の仕事に明け暮れ、同様に各班から隊員が班長として残り後輩の指導に当たった。
こうして青年たちが活動を続ける一方、国の補助金獲得は困難を極め、農拓協での資金繰りは赤字状態が続いた。神代組の受け入れ先となったコチア産業組合が資金不足を補い、獲得できた補助金は僅かな機械の購入費用に消えた。隊員らも農場の生産品をウムアラーマで販売し生活費を賄った。

6期生鈴木源治さん(73、山形)=サンパウロ市=は、「綿の収穫期は全員で綿摘みをし、日当に換えた。軽い綿を最低1人10キロ摘むのは一苦労だった」と振り返る。得たお金で調味料やピンガを買い、資金難の時は農拓協に預けた貯金を切り崩した。
食べ盛りの青年らに食料は一番の関心事。パン作り、漬物作り、魚捕り—各自が興味に任せて試行錯誤、その収穫を皆で分け合った。
ブラジルに貢献するという一大使命感を抱いて渡航し幻滅を感じた若者もいたものの、鈴木さんは「おかげで粗食に耐えられる生活力が出来た」と前向きに受け止めている。
渡航前、建設機械関係の会社で働いていた小山徳さん(72、長野、8期生)=サンパウロ市=は、「訓練所では実体験を積むことができた」と言う。
機械班として訓練所外で下請け事業を担当し、グアタパラ移住地で上排水ポンプの設置や機械類の修理に携わった。
訓練所卒業後はNECへの入社機会を得た。通信網が整いつつあった当時、青年隊から約40人が同社に就職した。鈴木さんもNECに勤めたが、その後測量士として独立した。ウジミナス製鉄所、イシブラス造船所、イタイプ発電所のダム工事など、多くの隊員が技術分野で就職し、中には事業を起こした隊員もいた。
仲間とイラセマ農場を経営し米、大豆栽培、肉牛飼育などで成功を収めた本間さんは、「機械の整備も運転も全て自分たちでやった」と胸を張る。農業に進んだ隊員にとっても、技術者でもあることは強みでもあった。隊員の約7割は農家出身、3割以上は農業に従事したといわれている。(つづく、児島阿佐美記者)