ブラジル文学に登場する日系人像を探る 10=中里オスカル=ジャブチ受賞『NIHONJIN』=中田みちよ=(2)=無防備な移民女性を描写
ニッケイ新聞 2013年8月1日
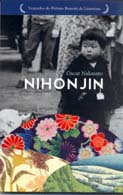 写真=本の表紙
写真=本の表紙
つぎに収容所から耕地に到着し、寝床つくりから始める農場のこまごました生活が語られますが、作者がブラジル人だと感じられるのは、女主人公のキミエが黒人女と友だちになることです。これは書き手が日本人一世なら絶対に出てこないシチュエーション。日本人が描く農園風景は、日本側に引き寄せられているんですが、この作品はブラジル側に日本が引き寄せられています。なるほどねえ、と感心しました。黒人女や現地の労働者たちが非常に好意的に、こんな言い方が許されるなら、肉親的な情がこもっています。
二人は、日本人の女と黒人の女は友だちになった。後にキミエの、黒人の家にキャベツを持っていった冒険劇を知った秀雄は、「あいつらにかまっちゃイカンといっただろ。野蛮なやつらだ。危害を加えられたらどうする?」
「ちがうワ」とキミエは否定し、こうつづけた。
「わたしたちと同じように働く人たちよ」「いいや。もう、話に行っちゃいかん。いいな」
稲畑は構成家族として若者ジンタロウを連れてきていますが、コーヒー園の労働者小屋に寝起きしているわけですから、隣室の夫婦の動きが手に取るように分かり悶々とします。また、いつも夫から怒鳴られているキミエに同情もしていますから、二人の結びつきは不自然でもないんですが、キミエはあくまでも受身で犯されるんだから、私は悪くない・・・と考えたりして、どんな瞬間にもいい逃れを模索する女性です。
実際には無防備な家庭内で乱暴された女性も数多くいただろうと推測するのも難しくありません。キミエは善良でまるっきり無防備で、キミエだけでなく、当時の日本女性一般は無防備すぎるような気がします。
そして、渡伯の手段としてにわか作りの家族が多数つくられたわけですが、孤老となった男性のほとんどは、この構成家族だったと、後年の調査で明らかにされています。つい最近、日伯援護協会が孤老の増加に悲鳴を上げていると邦字新聞が報じてもいました。
ジンタロウは俳句をたしなむ文学青年です。鬱屈した心情を吐露するための手段として、まもなく日系社会で盛んになる短詩型文学をしっかり登場させていて、目配りもきいています。
いつからか、ジンタロウの視線から、それはいつか起るだろうと、キミエは察していた。二人のとき、それは秀雄が近所の誰かと共同の野菜畑について話すのに出かけたときだった。いつもは寡黙でオハヨウもいわないジンタロウが、台所で後ろから抱き付いてきた。うなじに熱い息を感じたキミエは振りほどこうとした。彼女は、貞淑な女だった。雨に打たれ、風に吹かれる石のように泰然と、夫以外の男と寝るなど考えることすらできなかった女だった。なのに、奇妙なことに、力強い腕に快い衝動を感じた。けれども、振りほどこうともがいた。しかし、男の腕は強く説得力に満ちていた。いつも女であるより妻だった彼女がずるがしこくふるまえるはずがない。彼女は単純にただ思った。じっとこのまま立っていたって、私の落ち度などでない。男のほうが何倍も力が強いのだもの。彼女はもがくのをやめ、やめたのは疲れたからか、彼が動作を続行して欲しいからなのか、と考えていた
山中の閉ざされた生活体験がある私はキミエの絶望感がよく理解できます。男には、それが原因で落伍した者が大勢いたとしても、ピンガがつかの間の息抜きをもたらしてくれました。しかし女は弁当を作り、野良に出る以外は何の楽しみもない。むかしの男は、女にも感情があるということなど念頭になかったんですね。
ジンタロウは出立し、キミエは病気になります。ジンタロウが原因ではなく、(キミエはそれほど自意識がなく、単にカワイソウな女として登場)もろもろの積み重ねから、いまなら「欝病」とよばれたかもしれません。コーヒーの白い花を雪と勘違いして、その中で舞いながら死にます。ここでは雪が望郷心「サウダーデ」のメタファーとして扱われています。(つづく)


