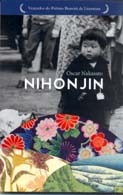ブラジル文学に登場する日系人像を探る 10=中里オスカル=ジャブチ受賞『NIHONJIN』=中田みちよ(3)=暴力的な父の下で成長する子
ニッケイ新聞 2013年8月2日
第2章は、やもめになった稲畑秀雄が新しい家族をつくります。キミエが生きていたころ、もらい風呂にきていた三木村さんの娘静江と再婚しました。早い話が、農作業の人手がほしいために結婚し、結婚させるわけです。農村部では結構、こんな感じで嫁入り話が進められましたね。実際には秀雄が入り婿のような形ですが、みんなで力を合わせて土地を買い、食用に豚を殺す様子や、戦前の結婚式の様子などが描かれています。最近のすぐ同棲する世相に比べれば、昔の人たちは義理堅いというんでしょうか、ちゃんと手続きを踏むんですねえ。
【それから父親が立って贈られた祝儀に謝辞を述べ、貧相な披露宴をわびた。酒宴には酒が欠かせないのだが、それはかなわずピンガ酒とリモネドでがまんしてもらわなければならない。饅頭のかわりに揚げたタピオカ芋。それにおにぎりとトウモロコシのケーキがご馳走だった。それでも、集まる機会がなく、祝いごとなど稀であったから招待客はみなご満悦だった】
【結婚式で女たちはリモネドを、男たちはピンガ酒をしこたま飲んだ。新郎までも度を越した。酔いが羞恥心をとりさり、調子はずれの大声で歌った。酔わないものは手拍子をとってリズムに合わせた。そのうち、男たちは抱き合い、花嫁の父親は泣き出した。歌いながら泣く。みんなも互いの心を計りながら泣きあった。泣くのは娘が結婚したからばかりでなく、涙が故郷を思わせるからでもあった】
静江はキミエと違ってはちきれるほど健康でしたから、次々と子どもが誕生します。舅と秀雄は肝胆あい照らす仲となり、家族は夢中で働きました。日本男子は暴力的でしかも周囲に馴化できないから閉鎖的。こんな男性像が現在でも数多く存在していますけれどね。
【当時の男たちは総じて暴力的だったが、それはつまるところ、ブラジルの大地に腹を立て、灼熱の太陽に怒っていたのであって、移民たちの苦痛と絶望を昇華させる代替行為だったともいえる。そしてブラジルにとどまることを受容したとき、異土を拒絶しなくなった。しかし秀雄は何年たっても受け入れられずにいた】
第3章は秀雄の子どもたちが成長し、田舎の学校に通学するようになって、文化の差、アイデンテイテイの問題をつきつけられます。三男のハルオは小さい時から、男たちの食事が終わってからでなければ食べられない母や女たちに不満でした。食事は家族全員が同じテーブで和気藹々とするものだ。モデルとして近所のブラジル人家庭がありますからね、いつも不満でいっぱいでした。
【「お前の心、それは日本人の心だ。お前は日本精神をもっている。顔もそうだ。その辺をブラジル人だといって歩いてみて、どうなる? 誰が見たってお前は日本人なんだから」まさしくそう考えていた。顔の輪郭もつぶれた鼻も、つりあがった目も。名前と同じように身体もそれを証明しているではないか。
「お前の名前はハルオだ—ブラジル人だったらジョアンとかアントニオとかジョゼだろう・・・」とつづけた。
するとハルオは切り返した。「お父ちゃん、顔や名前は変えられないし・・・それはあまり重要なことじゃないんだ。ブラジルガッコのセンセはみんな同じ神の子だというんだ。目がつりあがっていてもいなくても、髪の毛がまっすぐでも縮れていても、黒人の子どもでも、日本人の子どもでも・・・大事なのはお父ちゃんがいうように心なんだ。ぼくは自分はブラジル人の心を持っているように思うんだ」
「バカモン」。ハルオは力いっぱい横っ面をはられ、たちまち目が涙でいっぱいになった】
わが家の息子たちを想起した場面でした。お前たちは日本人だといわれ、それを信じて疑わなかった幼年時代。中学生になってからブラジル人だと自己主張するようになり、それを受容できない親の前では沈黙した子どもたちの傷。今なら見えるんですが、当時は不明でしたね。
3章の教室風景、これは田舎のエスコーラ・ミスタですが、なんとなくオズワルド・デ・アンドラーデの「ゼロマーク」と重なります。もしかしたら、オスカルさんも読んだのかなあと推察しました。相似点がありますから、マルクスなどにかぶれた学生時代に読んでいるかもしれませんね。(つづく)