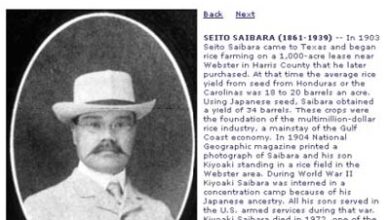日本移植民の原点探る=レジストロ地方入植百周年 ◇戦後編◇ (96)=戦後に呼び寄せ組合を創立=サンパウロ州移民再導入の先駆けか

いち早く連合青年会を1947年に発足させたのは、子弟教育が行き届いていないという焦りもあった。《レジストロ地方の子供が次第にカボクロ化してゆきつつあるのは事実だ(中略)町は一般に退廃的な点がうかがわれる。田舎での同化は退化と同義語といってよい》(『曠野の星』1954年2月、第22号、29頁)とある。
草分けの伊東重彦は《レジストロを健全な植民地にし、将来の発展性を作るには外来者を入れなければならない。進歩的な異分子が入って刺激し、摩擦し、現状を打破して新しいものを建設して行ってこそ新しいものが創られていく》(同29頁)と語っている。
古いがゆえに停滞した植民地の雰囲気を打破するために、外来者を入れ、健全な発展につなげたい――との機運が高まっていた。
松村昌和も遥か昔の記憶をたどる。「1951年に日本力行会の永田先生がレジストロにきて講演した。それまで日本から芸能団、スポーツ使節、代議士も来てくれておるけどね、誰ひとり、『日本が戦争に負けた』という人がいなかった。永田先生が初めて『日本が負けた』ってはっきり言った。戦争が終わって5年にもなるが、日本の一番の問題は学校を卒業しても職がないこと。そういう人たちをブラジルに呼んで欲しい」と講演した。
それが動機となって、「父(栄治)が先導して同志20人を集めて呼び寄せ組合を作った。父はコチア組合の評議員もやっていたから、評議員会で提案しているんですよ。『レジストロでこんな運動している』って。それがコチア青年の呼び寄せのきっかけになったと聞いている」という。
勝ち負け抗争の余波で、問題が集中していたサンパウロ州への日本移民導入はブラジル官憲が嫌っていた。だから53年に移民再導入が始まった時、最初に特別枠が許されたのはヴァルガス大統領と直談判したアマゾン地方の「辻移民」と南麻州の「松原移民」だけだった。
昌和はいう。「パウリスタ養蚕組合にいって養蚕移民を日本から呼び寄せる運動も父がやった」。これが移民審議会からサンパウロ州に許可(53年8月)された戦後初の日本移民枠となり、翌54年に第1陣の多くがモコカ市のアスパーゼ植民地に入った。この流れで第2回養蚕移民として55年に小野正安は家族7人で松村農場に入り、後に転地した。その時15歳だった長女が中田みちよ(『ブラジル日系文学』編集長)だ。
『曠野の星』22号(18頁)で村松栄治本人がこう語る。《我々一世はすでに老境に入りかけてきており、二世に良い指導者を与えなかったら郷土の真の繁栄は作られない》。さらに《毎月一人ずつ日本から特殊な技術者、たとえば畜産技師、水産技師のような人を呼び寄せ、此の地帯の産業改革をやるべく既に実行に着手している。日本から一人を呼び寄せるのに船賃十コントを支出してやって毎月一人ずつ呼び寄せるために「移民呼寄組合」を組織し、毎月五百ミル宛(拠金一口)とし、最初二十口、月十コントずつ集め、信濃海外協会、永田力行会長、原(梅三郎)日伯協会長当りと連絡をとって、新人をどしどしこの地帯に入れ、レジストロ建設運動に乗り出しているわけだ。第一回は十二月乗船、次は一月乗船のことに決している》と鼻息荒く語っている。
『曠野の星』54年2月号の取材をしたのは前年末だろうから、呼寄組合第1陣は53年末で、養蚕移民は54年、コチア第1回は55年9月到着という順番だ。同地独自の小さな取り組みがサンパウロ州への突破口を開いて養蚕移民で正式になり、コチア移民が本格化させたという流れだった可能性がある。(つづく、深沢正雪記者)