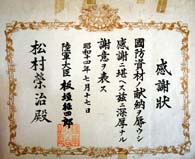日本移植民の原点探る=レジストロ地方入植百周年 ◇戦後編◇ (113)=紅茶輸出激減した90年代=全伯で唯一残る天谷製茶工場

朝6時すぎ、見渡す限りのお茶畑には、朝モヤとも朝霧ともつかないシトシト雨が降り注いでいた。緩やかな丘一面に等高線に沿ってお茶の畝が延々と続く。「昔はこんな光景は当たり前で、あちこちにあったんですよ」と福澤一興は説明する。ブラジル広しといえど、こんな光景はここだけだ。
紅茶工場としてはブラジル唯一となってしまった「天谷製茶工場」への最大の生葉(なまは)提供者の西芦谷和一(にしあしたに・かずいち)の茶畑だという。「生葉生産者は今では5軒程度しかのこっていない。もちろん、ほとんど日本人です」(福澤談)。
☆ ☆

80年代に紅茶輸出が良すぎたことが、〃もろ刃の剣〃だった。シャーブラスに42年間勤めた金子国栄は「輸出に頼っていたのが、逆に命取りになった。80年代、デルフィン・ネット蔵相の頃は為替を無理に低く抑えていた。政府が為替を低くしている見返りに、輸出額の6%の補助金を出してくれていた」という。
さらに「景気が一番いい時に本格的に国内販売の宣伝をしなかった。輸出ばっかり考えていた。長い目で見たら、国内販売を増やしていたらお茶工場を閉めるようにはならなかったと思う」と金子は振り返る。シャーブラスも10年ほど前まで営業していたが、今は活動していない。原沢和夫も「破産しないよう、赤字になる前に事業を清算したが、会社自体はまだ続いています」という。
金子は「50グラム×2億人=1万トン」という数式を書いた。これは国民一人が年平均50グラムの紅茶を飲んだら、最盛期の生産量1万トン超を国内消費でまかなえた可能性を意味する。
加えて「輸出はインドやセイロンと競争になる。向こうは人件費がすごく安い。でもこっちは最低給料やガソリンがどんどん上がるが、売値は上がらない。だからやっていけなくなった。90年代に、よそのお茶がもっと安く買える、ブラジルのお茶は買いません、っていうことになっていった」。足元南米の競争相手は亜国だった。
亀山譲治も「プラノ・コーロル(1990年)で潰れた。為替が大きく変動してダメになった」という。福澤も「農村労働法の導入(70年代)によって労働者の待遇確保が以前より大変になったことも一つの原因」と見ている。
福澤は「シャーリベイラも07年に工場を閉鎖したと聞きました。今、残る製茶工場は、天谷(あまや)さんだけです」と語った。
☆ ☆
巨大な製茶工場に入った瞬間、強力なお茶の「アロマ」がプーンと鼻をついた。お茶を飲んでいるときに鼻に登っているあの匂いだ。
21本の乾燥台はそれぞれ幅1メール、長さ20メートルほどもあり、うち4台にお茶が30センチほどの厚さで敷かれている。奥の方から4人がひと組になって、お茶っ葉を揉んでから放りあげ、かき混ぜる作業を繰り返している。
製茶工場の経営者、天谷良吾(りょうご、58、二世)=13年3月12日取材=は、「父の話では、かつてこの近辺には42のお茶工場があった。でも今はここ一つ」。そう言って、少し沈黙した。お茶畑の上には諸行無常の風が吹き渡っているようだった――。(つづく、深沢正雪記者)