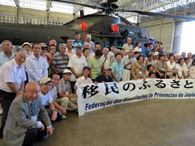県連ふるさと巡り=開拓古戦場に思い馳せる=パライバ平野と聖北海岸=(14)=サンセバスチャン=霜の降りない温暖地で野菜=車エビ漁や海苔生産で栄える
ニッケイ新聞 2014年4月15日

天井がなく、梁や屋根裏むき出しの会館には地方の趣が漂っている。裏にはゲートボールコートが3面あるが、舞台には備え付けのマイクもなく、カラオケ教室もないようだ。でも森会長によれば年3回のビンゴを実施し、9月のヤキソバ祭りには500人分が売り切れるという。12月には餅つきも恒例で、180キロを搗くというから本格的だ。
元会長の内山田太さん(80、福岡)は1959年に呼び寄せで渡伯した戦後の農業移民だ。最初はイタカケセツーバに入ったが、霜が降りて痛い目に遭い、「霜が降りない場所へ」と海岸山脈をおりて温暖なこの地へ66年にやってきた。以来トマトやピーマンなどの野菜生産に従事してきた。「サンパウロ市の方で霜が降りるとセアザの値段が3、4倍に上がる。そうするとこっちは儲かった」と思い出し笑いする。

サンセバスチャンは1636年のポルトガル人入植から始まる歴史ある港町だ。「日系漁師も5、6家族いた」というのは住川和代さん(65、和歌山)だ。1960年に家族で渡伯した。
和歌山県田辺といえば今も漁港で有名だが、父山崎登さん(故人)はそこで漁師をしていた。来伯当初はモジのコクエイラ区の養鶏場で働いたが1年後にはここへ来た。「わざわざ日本から漁具を送ってもらって始めたんです」。
エビやイワシ漁が一般的だが、山崎登さんは車エビ中心で、セアザに送っていた。父について仕事を習っていた住川正吾さん(二世)と和代さんは結婚した。70、80年代が最も景気がよく、「昔は同じところで1カ月も2カ月も漁をしていた」と懐かしむ。「だけど今は15分遅れて着いたらもうないって。だんだん収穫が減って…、取り過ぎらしいです」。
「今は日本人の漁師はいません」という。「海の上では『板子一枚下は地獄』と言いますが、夫が漁の最中に危ない目に遭ったりはなかったのですか」と尋ねると、「父も夫も危険があったとは一言も言いませんでした。でも、きっと怖い目に遭ったことはあったでしょうね」と思いやった。

加治屋八重子さん(68、二世、スザノ生まれ)は「鹿児島生まれの御爺ちゃんが、ここに視察に来たとき『イーリャ・ベーラが桜島にそっくりだ』って思って、住むことに決めたそうです」という。その祖父も7年前に亡くなった。
加治屋家を初め、同地には最盛期で6軒も日系海苔生産者がいたという。八重子さんは「岩についた海苔を地元の人に拾ってこさせて、それを買い取って集める。それをマダラにならないように均等に薄く延ばして乾かすんです。立ちづめの仕事で重労働、あの当時『嫁さんは手先が器用でないと務まらない』と言われた」と日本の農家のような話を思い出しながらする。
日本と同じサイズで日産1500~2千枚というからかなり多い。「でも日本製が入ってくるようになって競争が厳しくなり、1992年頃に辞めました。やっぱり日本のは青々としてキレイですから」と残念そうだ。
「四世の孫も『フリカケくれ!』って言うんです。やっぱり海苔が好きなんですよ」とほほ笑んだ。
「私らがここに来た1950年頃、日本人は3家族ぐらいしかいませんでした」。永井文子さん(90、福島)は1927年、3歳で渡伯し、最初はオーリーニョスに入った。生まれたのは福島県双葉町、東日本大震災の原発事故が起きたあの町だ。今は放射能で大きな被害が出た故郷について質問をすると、数秒沈黙し、戸惑ったような表情を浮かべた。(つづく、深沢正雪記者)