駐在員をテーマーとするショート・ショート連作=「ブラジル諸人来たり」ブログより許可をえて抜粋=(2)=UFO
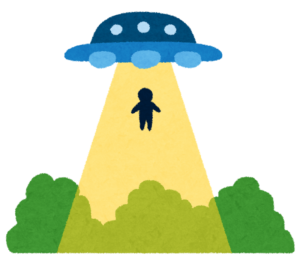 「工場長、この辺はよくUFOが現れるそうですよ。というのは、真っ赤な嘘ですが」と、私より半年ほど早く、ブラジル支社に就任していた後輩の矢柄が言った。
「工場長、この辺はよくUFOが現れるそうですよ。というのは、真っ赤な嘘ですが」と、私より半年ほど早く、ブラジル支社に就任していた後輩の矢柄が言った。
「馬鹿野郎」と、私は親愛の情を込めて、後輩の頭を小突いてやった。しかし、そう言われてみれば、UFOが突然現れてもおかしくないような、見渡す限りの荒涼とした世界であった。「よくもこんなところに工場を建てるなんて考えたものだ」と、支社長の小出の顔を思い出しながら内心そう思った。
「うちの工場の予定地としては、いいところでしょう、先輩?」
「そうだな…」と私は後輩の言葉に頷いた。
グッドアイデア、いやボーア・イデイアではあった。しかしその感想も、その工場予定地から二体の人骨が出て来た事で、ちょっと変わった。
もし遺跡の関係であれば、警察と市役所が間に入って来るので、問題がこじれると心配した。でも、会社の弁護士が金銭をちらめかせて交渉した結果、その二体の白骨は「古い心中死体だ」と言う事になり、工事は図らずも無事に進展していった。
また問題が起きたのは、それから一年ほどして工場が完成する間際になってからの事で、支社長の小出が、「この辺りはずっと以前にインジオの居住区だったらしい。その事を知った市が、工事をストップさせるように要請して来た。どうする、加山?」とえらく落胆しながら言った。ついているはずの話を蒸し返してきたようだ。
「そうですか。でも、ちょっとへんですね。市は我々がここで生産を始める事で、税金や雇用で得をするはずですよ。立ち退きを要求しているのは小役人の賄賂の要求ですよ」
「いいや、加山。わが社がここから立ち退く事を要求しているのは、実はアメリカのWH社が工場敷地としてこの辺一体を買い占める意向を伝えているからだという情報があるんだよ」
「WH社ですか…。UFOより怖いですね。本当だとすると随分と強引なやり方ですね」と私は答えた。
「でも立ち退く必要なんかありませんよ。ここは契約社会です。うちの社と市はすでに契約書を交わしているじゃないですか?」
「はっはっは、それもそうだったな、加山。はやとちりをして悪かった」と晴れ晴れとした表情を浮かべた。
日本からきたばかりの支社長には、市の小役人のゆすりがよほど堪えたのだと、私は同情を覚えていた。
しかし、アメリカ企業進出の噂は本当の事だった。それから二年ほどしてから、社の工場の横で、何倍もありそうな土地の造成工事が始まっていた。
「この辺もこれでにぎやかになるな、加山?」
「同感ですね。これだけにぎやかになれば、UFOも出て来れないでしょうね…」
私は支社長が、以前の不安を忘れてしまったような事を言っているのがおかしかったが、そう答えた。本物のUFOは出なくても、市の小役人達がUFOのように飛び回って、このアメリカ企業からもきっと幾らかせしめようと行動したに違いないと思った。




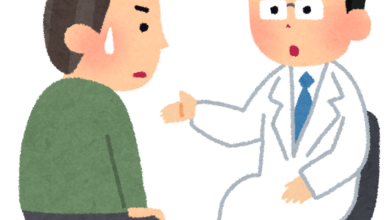
![(写真素材ぱくたそ[モデル:Lala]より)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2015/05/CL201_syorui2320140830185655500-thumb-1000xauto-5479-390x220.jpg)