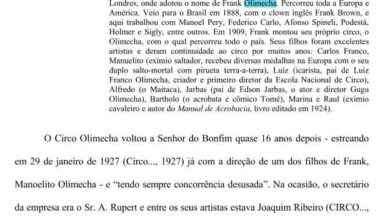軽業師竹沢万次の謎を追う=サーカスに見る日伯交流史=第13回=世界最大のサーカスがコンデ街に

突然だが、話は二十世紀に移る――。竹沢万次とは関係がないが、世界最大のサーカスが戦前、サンパウロ市の日本人集団地「コンデ街」にやってきた逸話は、日伯交流史には欠かせない。
1934年8月3日から、当時、世界最大といわれたドイツのサーカス団「サラザニ」がブラジル巡業に来て、なんと日本人街コンデ・デ・サルゼーダスのすぐ裏、「スダンのカンポ」に1万人収容の8本マストの巨大テントを張って興行を行った。そのスター芸人が日本人・沢田豊(1886―1957)とその家族であった。
沢田は16歳のとき、1902年に海外興行でロシアに足を踏み入れ、以後30年間も欧州などでサーカス生活を続け、サラザニCの看板スターにまで上り詰めていた。
1913年、ベルリンの音楽家の娘アグネスと結婚、6人の子供に恵まれる。1912年当時《ドイツに八組、イギリスに六組のグループがいたというから、第一次世界大戦前に相当の数の日本芸人がヨーロッパを舞台に活躍していた》(89頁)。
だが1915年から始まった第一次世界大戦中、ドイツにサーカスの仕事はなくなり、工場労働をしながらしのいだ。戦後ようやくサラザニCが復活し、沢田は再びアーチストに戻った。
しかし、1930年前後からナチス台頭の時代を迎え、ユダヤ人を多く雇う同サーカスに悪名高いナチ親衛隊が連日いやがらせに来た。ハンス・サラザニ団長はドイツ脱出を考え、一旦ケンカ別れしていた沢田を誘った。
「ブラジルには日本人がいるんだ。君も久しぶりに故郷に帰ったような気になるんじゃないか。それに南米興行の後に日本へ行く」との団長の殺し文句を信じ、祖国凱旋を夢見て、沢田は参加した。
戦前コンデ街に所在した「日本新聞」(翁長助成社長)が1934年8月22日付から足掛け5カ月、16回に渡って沢田豊の回想録を連載した。
実際、コンデ街にきた沢田は、《私が一番最初に飛び込んだのはうどん屋さんである。いきなり天ぷらうどんを二杯やり、のり巻き四本、おいなり四つをやっつけ、それから数日通って下痢をした。その他中矢商会で缶詰やら講談本を買いこんだのなんの、三十年振りのノスタルジアを満足させた》(186頁)とある。
沢田も移住者であり、外国生活の長いものにとって、やはりコンデ街は〃心のオアシス〃であった。
サンパウロ市の前、リオで沢田の娘が公演中に綱から落下して骨折した時、伯字紙が大々的に報道し、トメアスー移住地開拓事業を先導していた福原八郎がわざわざ見舞いに行った(『サ芸人』183頁)。
その時、サラザニCにはなんと約500人もの団員がおり、珍しい動物が何百頭もいた。象だけで30頭もおり、動物園のようだった。靴屋や鉄工場も設備する1万2千トン級の船2隻に設備一式を乗せて、移動するという〃小さな町〃という様子だった。
サンパウロ市公演は2カ月半も行い、たくさんの観客の中には目立って日本人が多かったとある。《ブラジルで成功した富農や商売に成功した人は、みんな正装して見にきた。なかには、ロバにのって三日もかけて奥地からサーカスを見にくる日本人もいた》(188頁)。おそらく、実際にこれを見に行った弊紙読者もいるのではないか――。
ただ、公演中に大事件が起きた。団長がサンパウロ市公演中の8月21日にドイツ病院オズワルド・クルスで病逝したのだ。
その後、亜国公演の終わり際に、団長の息子から沢田は呼ばれ、「日本公演は辞めた。ドイツに帰る」と突然申し渡された。ナチス嫌いだった故サラザニ団長に対し、息子は逆だった。そしてドイツに帰国した後に解雇を言い渡された。
コスモポリタン芸人ゆえに国際情勢の荒波の直撃を受ける人生だった。(つづく、深沢正雪記者)