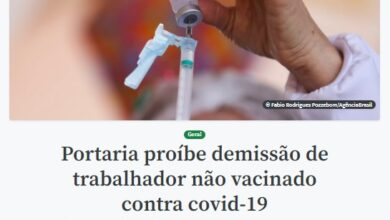ラヴァ・ジャット作戦の映画、興行1位=批評で相次いだ作品への批判
2014年3月以来、本紙でも連日のように報じているブラジル史上では最大、全世界規模でも屈指の汚職事件であるラヴァ・ジャット作戦を描いた映画「ポリシア・フェデラル~ア・レイ・エ・パラ・トードス(連邦警察~法は全ての人のため)」が、週末のブラジルの映画興行成績で、2位に4倍以上の差をつける740万レアルを売り上げ、1位に輝いた。
ラヴァ・ジャット作戦の発端は、結果的にこの大汚職事件の仕掛け人だということが判明した闇ブローカーの事件を追っているうちに、共犯者のひとりがブラジル経済の中心のひとつ、石油公社のペトロブラスの元役員であることが発覚したことだ。
この元役員の口から、同社の契約での利権を巡り、政権党であった労働者党をはじめとした主要連立与党と主要ゼネコン企業が、契約金の数%を賄賂として支払うという形で贈収賄工作を行っていたことや、その贈収賄総額が数10億レアルにまで及んでいたこともわかった。
そうした大事件を、現職政治家などを除いた被告の第1審を裁く地方判事、セルジオ・モロ判事が権力に屈することなく厳しく裁き続ける姿は、ブラジル国内だけではなく、国際的にも注目を浴びている。
この映画は、連日報道され、国民にはすっかりおなじみとなった事件を取り上げているということもあり、国民の関心も高い上、公開前から熱心に宣伝も行われていたため、このような成績を収めることは予想されていた。
だが、この映画を観たブラジルのメディアの映画評は、酷評が続く皮肉なものとなっている。
たとえばフォーリャ紙は「政治家は実在の人物を使っているのに、連邦警察は匿名なのはおかしい」と指摘。さらにオ・グローボ紙も「主役側の連邦警察捜査班のキャラクターの絞込みができておらず、ステレオ・タイプだ」と批判した。
さらにゼロ・オラ紙は「あらゆる政治家が絡んだ事件なのに(PTの親玉の)ルーラ元大統領だけが敵になっているのはおかしい。続編では(現政権の)民主運動党、その次は(労働者党の政敵の)民主社会党も描くべき」とした。
とりわけルーラ氏の描写には批判が集まっていて、「声色だけを物まねていて悪趣味だ」と称するものが目立っていた。
この映画に関しては、弊紙でラヴァ・ジャット作戦の記事を書き続けている筆者も観た。感想は前述のものと大体同じだが、少し付け足すとしよう。
まず、ハリウッドのクライム・サスペンスをまねたような大げさな効果音があまりにもステレオタイプなのが気になった。そこに加え、前述したような、キャラクターの見えない薄味の演技が続くために、悪い意味で型どおりなだけの映画に見えた。
あと、「連邦警察の宣伝の映画だ」との批評もよく目にしたが、そのとおり、あまりにも連警に焦点が当てられすぎていて、検察庁や裁判官の存在が無視されていた。前述のモロ判事も、国民への知名度を考えれば、彼がどういう人となりで、どんな勇敢な行動で尊敬されるにいたったかを知りたいところが、せっかく配役されていても、ただ存在しているだけのおまけに過ぎなくなっており、見る側の欲求不満が募りそうな気がした。
あと、ラヴァ・ジャット作戦では、この期間に在任したジウマ、テメルの両大統領や、ジウマ氏を罷免に追い込んだが、自らも汚職で職を追われ逮捕までされたエドゥアルド・クーニャ下院議長という絶好のキャラクターが存在したのに、彼らが登場しないのも肩透かしだった。
総じていえることは、事件はまだ継続している上、今も膨大なことが起きているにも関わらず、実に短期間で、本来ならテレビ・シリーズ向きの題材を無理やり映画にしてしまったという印象を免れ得ないということだ。
加えて、ブラジルの芸能界の場合、俳優は左翼の労働者党の支持者が圧倒的に多いため、役者集めに苦しみ、さらに監督も普段はコメディを作っている人物だった。こうしたところで既に無理はあったようだ。
ただ、題材としては魅力的なものであることはたしか。もうひと世代、あるいは二世代でネタをあたためて、決定的なものをそのときに見たい気もした。