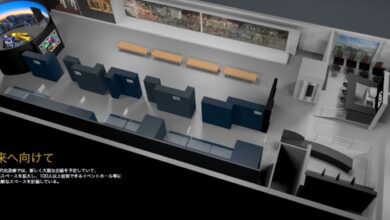《ブラジル》日・ブ折衷の陶芸目指して=-デカセギ新世代、福澤さん=(下)=ブラジル独自の作品を求めて

福澤さんは「18歳から勉強と会社勤めを経験し、将来に悩んできた。考え事をせず制作した後は一つの周期を終えたような感覚だった」と静かにふり返った。ブラジルに住む恋人との結婚を機に帰国を決意した。
日本各地の伝統陶芸に触れてきた福澤さんは、「歴史がなく資源の豊富なブラジルだからこそ無限の可能性があるのではないか」とブラジルの土を活かした陶芸の発展を目指している。現在はサンパウロ州内陸部から仕入れた土のサンプルを使った作品作りなど、陶芸向きの土探しもしている。
福澤さんが日本で陶芸作家を訪問する中、「大量生産による伝統工芸への弊害」を目の当たりにすることもあったようだ。「伝統工芸作家の収入が少ないため、とにかく跡継ぎがいない。その日会ったばかりなのに『窯も工房も全部やる』と言ってきた人もいた」と振り返り、「でも僕はブラジルで『日本の陶芸』をやるつもりはない」ときっぱり否定した。
理由を聞くと、「いわば『ミックス』の僕に日本の陶芸は作れない」とのことだ。
30代頃、制作や日常生活の中でアイデンティティーに悩むことがあったそうだ。ブラジルにいれば「日本人」、日本では「ブラジル人」として扱われる。「あと例えば、笑いのツボは日伯両方わかる。でも『空気を読む』ということはできない。陶芸でも『しっくりくる形』がわからない。一生感じ取れないと思う」と身振り手振りを交えながら説明した。
その悩みを沖縄県の彫刻家、金城実さんに打ち明けると、福澤さんが日本の陶芸作りをすること自体を否定されたそうだ。「君が何百年の歴史を持つ日本の伝統工芸を作ろうとしても、その歴史に追いつかない。違う文化や感性を持っているんだから、それを活かすべきだ」と助言を受けた。
その助言で福澤さんを悩ませていた「気持ちの枷」が外れたように感じ、制作に対する気持ちが楽になった。「むしろ日系人という感性を作品に活かしていきたい」と新たな方針ができた。
しかし日本で陶芸を学んだことが福澤さんの「売り」になるのも事実だ。そういった経験を買われて制作を依頼されることもある。「皆特別なものが欲しい時代だからね」と淡々としている。
福澤さんはブラジル陶芸の成長のためにも、作家活動が軌道に乗った後に自分の知識や経験を知りたい人に伝えることも考えている。「あくまでも生活が安定した上でね。得た経験や知識を隠したまま死ぬのは意味がないと思う」と語った。(終わり、國分雪月記者)
□関連コラム□大耳小耳
レジストロの自然に囲まれた環境で育った福澤さん。手仕事が減り、便利化した現代社会に対し、「大事な感覚を失ってきているのでは」と警鐘を鳴らしている。現代の子供はスマートフォンで遊び、大人はパソコンで仕事をするなど土に触れる機会がなく、指先でなんでもできる時代。それに対し、「陶芸という、できるだけ原始的な方法でその『失った感覚』を取り戻し、作品で訴えかけたい」と語った。デジタル全盛期の現在、逆に「手で作る」ことの意味を、とことん問い詰める福澤さんの今後の作品に期待。