書評=『カヌードスの乱 19世紀ブラジルにおける宗教共同体』(春風社)=戦争の根底にある問題の本質を俯瞰=ブラジル学研究者 田所 清克
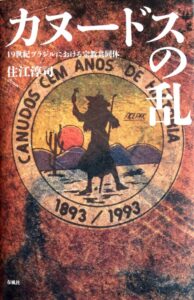
F・ジュリアンの『重いくびきの下で―ブラジル農民解放闘争―』(岩波新書)の書に表徴されるように、ブラジルの北東部、わけても奥地は、旱魃に加えて農園主や地方ボス(コロネル)による搾取と圧政による貧困が絶えず、革命的な文学が生まれ、と同時に社会運動が出来する精神風土があった。
バイーア州奥地を描くエウクリーデス・ダ・クーニャの手になる叙事的ノンフィクション小説も、奥地住民(セルタネージョ)の貧困を描いた社会文学と解されなくもない。その小説とは、雄渾にして清冽なリリシズムがあふれる文体で、地理学や人類学などの学際的な視座から地域の自然景観と住民について記述しながら、カヌードス戦争を主題にしたOs Sertões『奥地』のことである。
この作品を通じて当の作者であるクーニャは、「もう一つのブラジル」と目される北東部の赤裸々な現実を国民の間に知らしめ、と同時に、「ブラジル人とは何か」を問うた点で内外の耳目を引くこととなった。
ノーベル賞作家のバルガス=リョサが、世界文学に匹敵する『奥地』に想を得て『世界終末戦争』のタイトルで作品化したのはよく知られたところである。そして、ステファン・ツヴァイクは同作品を「稀に見る偉大な叙事詩」と捉えた。他方、ブラジル南部を代表する地方主義者のエリコ・ヴェリッシモは、「もし自分がブラジル文学の中で外国語に翻訳・紹介するとすれば、『奥地』を選ぶことになるだろう」と述べている。ことほど左様に『奥地』は今や、文学のジャンルを超えてさまざまな研究領域で研究の対象となり、ブラジルの理解のための基本文献の一つとなっている。
ところで、ここで論じる『カヌードスの乱 19世紀ブラジルにおける宗教共同体』(春風社)の著者は、その前期近代主義時代に世に問われた、畢生の大作である『奥地』を読んだことが、自身のディシプリン、すなわちブラジル史を選ぶ動機になったと言う。
その気鋭の著者が、史実を踏まえた同作品のカヌードス地方の住民と州および政府軍との間に繰り広げられたカヌードス戦争(著者は「カヌードスの乱」としているが、数次に亘る戦争とその規模、死者の数から言って、評者は「カヌードス戦争」と捉えている)を研究テーマの中心に据えて考察したものがついに、好個の歴史書となって結実した。
カヌードス戦争が生起してすでに今年で121年を迎えるブラジルでは、これまで関連の研究がさまざまな視座から試みられ、結果としてそれなりの学問的蓄積もある。がしかし、日本でのこの方面の研究となると、一部の文学論を除いて皆無に等しい。写真家の小田輝穂の『カヌードス・百年の記憶―ブラジル農民、土地と自由を求めて』(現代企画室)の書の他に、評者は寡聞にして知らない。
その意味において、著者による『カヌードスの乱 19世紀ブラジルにおける宗教共同体』の上木(出版すること)は、日本におけるブラジル史研究、わけてもカヌードス戦争に関する研究の濫觴を成す画期的なものだ。と言うのもそれが、カヌードス戦争のテーマに着手した日本では先駆的なものであることに加えて、現地で渉猟した歴史史料、ブラジルの専門家との密なる意見交換、さらには、度重なるフィールド調査などから得られたカヌードス関連の知見と成果を遺漏なく踏まえて、史上最悪の内戦の全貌を見事に素描しているからに他ならない。
論述の過程で著者は、住民の精神的な支柱であったメシアニズムやドン・セバスチャン信仰などに端を発する戦争の要因について多くの紙面を割き、専門家たちの言説や論点を丹念に整理・解釈することに注力した跡がうかがえる。
中でも圧巻なのは、カヌードス戦争の理解に向けては不可欠な要点ともいえる、千年王国運動などの宗教的な事象に光を当てるのと併行して、一人のカリスマ的指導者の下に集った、貧困にあえぐ邪教徒(ジャグンソ)とみなされるカヌードスの住民と、対峙・敵対する教会、農園主、州および政府との関係をつまびらかに論じることによって、同戦争に係る問題の解明に迫っている点だろう。
同様に、セザル・ザマの手になる書『カヌードスの乱に関する実録を伴うブラジル共和国への嘆願書』を礎にした、カヌードスの乱(ママ)が共和国に対する叛乱であったか否かの論点に関しての、著者の的を射た解釈には説得性があり、同時にカヌードス戦争の根底に横たわる問題の本質を俯瞰・展望できるようになっている。
さらに特筆すべきは、末尾に付記したリオデジャネイロ陸軍省公文書館収蔵の関係資料であろう。重要史料の数々が列挙され、カヌードス戦争研究を進める上では欠かせないものだ。
望蜀(編注=次の望み)の言ながら、カヌードス戦争前後に、宗教にも結び付いた、例えばセーラ・ド・ロデアドルやカルデイランの乱、コンテスタード戦争などが生起している。これらへの言及と比較考察がなされていたならば、カヌードス戦争の全容が一段と浮き彫りにされ鮮明なものになったのではないか。
カヌードス戦争を論じた部分ではないが、書の劈頭で著者は、可視的、有形的な面では多様なブラジルは、無形的な面、すなわち人々の価値観や行動様式の面では比較的「均質」である、と述べている。が、果たしてそうなのか。この点においては少なくとも評者の見解とは異なる。と言って、本書の価値をなんら傷つけるものではない。
とまれ、博士論文を補筆して編まれたと思われる本書が、日本における新たなブラジル史研究に一石を投じるものになったのは寸毫の疑いもない。ブラジルではいまだ、「土地無き農民運動」やマイノリティ等に象徴される社会運動の類が散見される。この種の問題を考える上でも本書が示唆するものは少なくなく、それだけに歴史研究書として高く評価できる。
[田 所 清 克 (ブラジル文学、民族地理学を基盤としたブラジル学)


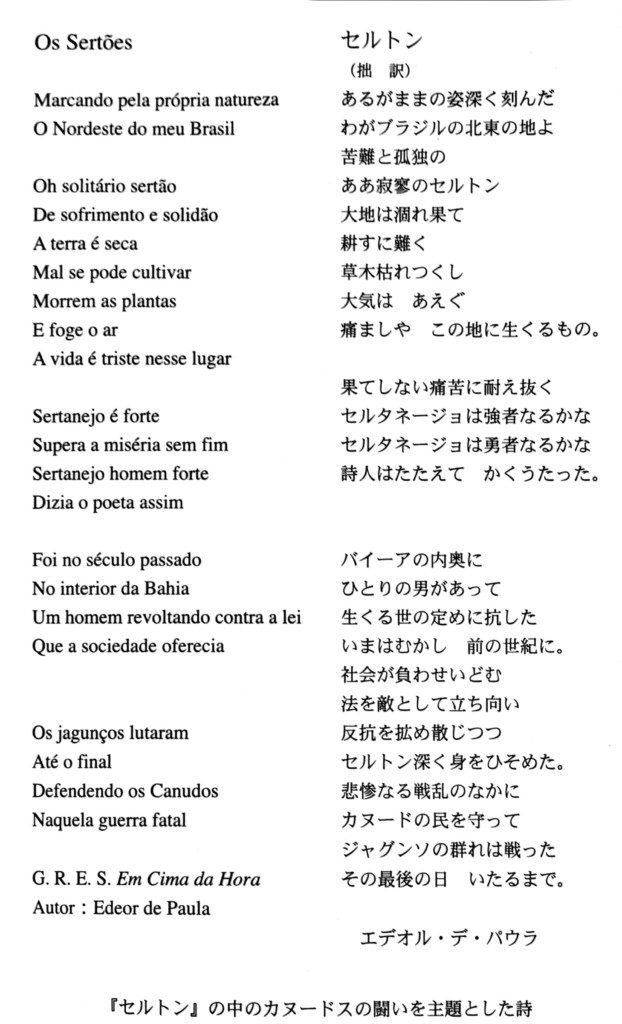
![ストロエスネル大統領( [Public domain], via Wikimedia Commons)](https://www.nikkeyshimbun.jp/wp-content/uploads/2017/10/Alfredo_Stroessner2-333x220.jpg)


