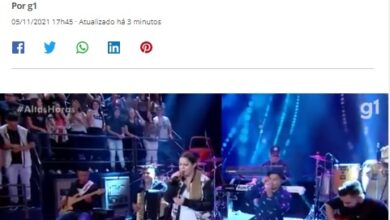臣民――正輝、バンザイ――保久原淳次ジョージ・原作 中田みちよ・古川恵子共訳=(121)
正輝、房子夫婦には数ヵ月前の悲しい事件のあと、ごくあたりまえの家族に戻ったように映った。だが、両親にとってはあたりまえのことだが、息子のひとりにとってはあたりまえではなかった。次男のアキミツは、長男以外のその他大勢の子として扱われた。それは子どもに対する両親の言葉、態度の差にはっきり表れていた。家庭で長男はいちばん大事にされるのに、アキミツはニーチャンのような扱いをうけることはなかった。言葉が分るようになっても、その状況が変わることがなかった。日本人の父母は自分たちのいうことに従わない子どもの反発などに無頓着だ。とくに母親の房子は自分の立場に不満をもつアキミツに耳を傾けるようなことはなかった。
彼は「どうして、長男にほとんど全部やって、他の子にはその残りしかやらないの?」
母を怒らせないため、できるかぎりの知恵をしぼって、注意深く聞いたが、そんな努力は無駄だった。
「そんなこと聞いてどうするの? これはお父さんとわたしが決めたこと。二度とそんなこと聞かないでちょうだい」と叱られた。
子どもにとってその答えはなんの説明にもならない。
「だから、そういうことなの」
まるで、息子を納得させたように母はそう答えた。
アキミツは日本人家庭での長男の立場を他の子どもたちより真剣に考えていた。兄との年齢の差が近かったので、差別から受ける苦悩をはっきり感じていた。少しだけあとから生まれたということだけで、権利や恩恵がやみくもに否定され、削減され、取りあげられたのだ。服を買うときはいちばん上等な服が買われ、食べるときはいちばん先に、そして、いちばん大盛りの食べ物が与えられ、歩くときはみんなの先頭を行く。両親の愛情は彼にだけ向けられている。
「どうしてなんだ?」アキミツは自分に問いつづけた。
それは日本人家庭によくある「次男の悩み」だった。兄弟のなかでは、次男がいちばん両親の差別を感じる。
保守的で人間的感情や価値をあまり認めない環境(二十世紀初めの貧しい沖縄の農村)で育ち、教育を受けた房子は子どもの教育については、自分が受けた観念を植えつけることこそ最良だと信じて疑わなかった。
渡伯以来、悪条件の上に、しかも、自分の家で姪のウサグァーが殺害され、ヂフテリアで病院に運ばれるなか息を引きとった三男ヨーチャンの死という二つの出来事以来、房子は長男以外の子どもたちの気持ちをくみ取れないようになっていた。
日本人が優しさをこめた子どもを呼ぶ「ちゃん」を嫌った。ただ、ナオシゲだけはヨーチャンとよんだ。幼くて逝ってしまった息子に対する、後悔の念がそうさせるのだ。子どもの扱いには距離をおいた。優しい態度は全くなかった。
別に子どもが嫌いだったわけではない。沖縄の習慣ではたとえ親子であれ、べたべたしないのが普通だった。
アキミツがニーチャンが受けている母の注意を自分に向けさせようとすればするほど、母はますます無関心になった。房子の無理解、子どもの気持ちを分かろうとしないと決めた母の思いがそうさせたのかもしれない。そして、二つの磁石の同じ極が反発するような兄との関係がつづいた。二人は長い歳月を経たあとに、そのことに気づいた。