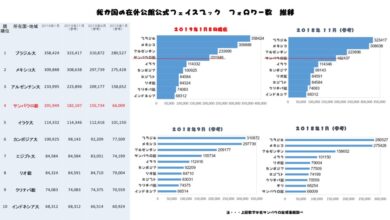「ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反故のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼び覚まし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを」(カミュ『ペスト』宮崎峰雄訳新潮社)
パンデミックで混乱する世相を予言した『ペスト』
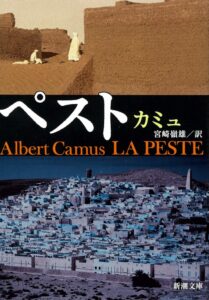
フランスの哲学者であり、ノーベル文学賞受賞者の文学者・アルベール・カミュが1947年に発表した小説『ペスト』では、厄災は必ず復活するという予言を遺して終わる。
新型コロナウイルス感染拡大が続き、外出自粛要請が発令されている最中、自宅待機中の人々が『ペスト』を読んでいるという。日本全国の書店では、この本が在庫切れになるほど売れ、文庫を発行する新潮社は15万部以上の増刷を実施。累計販売100万部を達成したという。
この現象は世界的にも広がっているということである。私も以前に読んだこの本を、インターネット文明の恩恵にあずかり注文して、即座にアイブックで再読した。
何故今この『ペスト』が読まれるか
否、未来に、今起きているような疫病との闘いが起きた時には、必ず、繰り返し読まれるであろう。
それは、いまだかつて、このような状況を経験したことがない者は、今何が起きているか。感染病とは何か。
もし自分が、家族、友人が罹ったら、その状況にどう向かえばよいか…、現状を冷静に、客観的に知りたいとおもうからである。
カミュはこの長編小説を、ドキュメンタリーのように、粛々と書いて遺した。これこそ「未来の記憶」として。
この物語は、第2次世界大戦の2年後、1947年に発表されていることにも注目したい。戦争による殺戮と、破壊から世界が立ち直ろうとしていた時である。戦後まもなく、世界が戦争の惨禍から解放されて、人々の気持ちが自由に開放されたところへ、差し出された、何事かを暗示する一書であると考える。
事の始まりは4月、公的に終息宣言されるのは、翌年の1月25日、約9カ月間の疫病との闘いの記録である。
伝染病との闘いは、戦争のように人間同士が殺し合うものではない。疫病は個人だけでなく、社会全体を襲う。社会的機能は停止、最悪の場合、都市封鎖、人々は孤立し、限界の中で死ぬ。
病魔は人を選ばす、高貴な人、宗教者、一般庶民、そして、医師も疫病地獄の闇に陥ることになる。全く得体の知れない、目に見えない、しかも高い致死率の病魔との終わりの読めない闘いである
それだけではない。終結宣言が発せられた時の人々はどのように生活を再構築するか。愛する者を亡くしたこと虚しさ、幽閉状態に置かれた時間を取り戻せるのか。
私たちがこれから迎える疫病の終息後の生き方についても、暗示しているのである。
それでは、ここに何が書かれているか。どこが今の状況に酷似しているのかを「傾聴」する。「傾聴」とは、全身全霊で耳を傾け、誠実に、熱心に聴く、ということである。
疫病は突然現れ、音もなく消え去る
物語は、フランスの植民地であるアルジェリアの実在するオラン市。そこは小さな港町で、人々は金儲けに専心し、土・日の休日には大いに遊ぶ。戦後の近代世界のどこにでもある町の風景である。日常生活上での不満、不便、嫌悪はたくさんある。
しかし、そこで暮らすうちに、人々はそれらのことに「慣れ」て自由に生活を営んでいる。
1940年代のある4月16日の朝、主人公の医師、ベルナール・リウーが診察室の前の廊下に転がった一匹の鼠の死体を見つけるところから始まる。
同じ日の夕方、自宅の玄関前で血を吐いて死ぬ鼠を目撃する。
そして翌日から市民は、あちこちで無数の鼠の死骸を見る。すぐに町は疫病によって地獄化していく。
数日後には8千匹もの鼠が死に、市民に多数の死者が出はじめる。医師のリウーは死因がペストであることに気付く。新聞やラジオがそれを報じ、町はパニックになる。急速に、毎日、死者の数は増える一方で、最初は楽観的だった市当局も対応に追われるようになる。
やがて町は外部と完全に遮断される。脱出不可能の状況で、市民の肉体的にも精神状態も疲労困憊してゆく。
隔離対策の実施
町では患者の隔離対策が進み、外部との接触が禁じられ、町の門の封鎖が始まる。
役人の対応
政府(小説では県庁)官僚や役人たちは当初、ペストであることを認めない。もしペストでなかったらその責任を負わねばならない。責任逃れに依る初期対応の鈍さが事態をますます悪化させる。
混乱する市民
巷を駆け巡る様々な風評に翻弄される市民。「俺は陽性だ」と叫んで街の女に抱きつく男。
博学で戦闘的なイエズス会の神父は、「これは人間の罪深さに対する神からの罰である。悔い改めよ」と厳しく説教する。一人の少年が苦しみながら死んだ。それも罪のせいだと言う神父に対し、罪なき者はこの世にはいないのではないか、と医師リウーは強く抗議する。すぐに神父もまた感染して亡くなる。
医師の信念を貫く、主人公リウー
リウーには結核療養中の妻がいた。
その妻を、遠く離れた療養所に移し、町に残って疫病治療の緊急対応に没頭する。結局、妻とは会えず、疫病終息後に死亡の報せを受ける。
たまたまこの町に取材旅行に来ていた新聞記者は帰国することができない。手紙も出せない。主人公の医師リウーに、出国のために感染者ではないという証明書を書いてほしいと懇願する。
しかし、リウーは、「医者は誠実でなければならない」という信念から、断固として彼の申し出を拒否する。
「緊急時だから信念などという抽象的な観念は棄てて対応しろ」という要求にも、「あなたが僕の診療室を出た瞬間から県庁に入る瞬間までの間に、病毒に感染することがないとは保証できない。この町の何千人という同じ状況の人たちを出してやるわけにはいかない」という理由である。
次々と運ばれる病人に対応しきれなくなった病院では医療崩壊が始まる。
一般市民による救援活動
ジャン・タルーという青年の父親は検事である。ある日、法廷で父親が犯罪者に死刑を求刑するのを見る。彼は人が人を裁くこと、しかし、裁かねばならない矛盾を受け入れらず、父との理念の違いから家出をして世界を放浪する。
そして、この町で生きることにしたタルーは、リウーと知り合い、作家志望の下級役人とともに、必死に治療を手伝う。救済活動のための団体を組織するが、病気で死んでしまうことになる。
災厄の終息
災厄は突然、潮が退いたように終息する。それは発生から9か月後の1月25日のことである。
人々は静かに元の生活に戻ってゆく。そして、リウーの周辺にいた人々は悲喜こもごもの結末を迎える。医療現場の最前線で戦っていたリウーも、結核療養中の妻が死んだことを知らされるのである。
災禍に「慣れる」ことと「忘れること」
小説の最後は、行政上の告示であるペスト終結宣言を聞いた直後からの市民の表情が語られる。
暗い港から、祝賀の花火が上がった。街中が歓喜に包まれるかというと、そう単純なものとしても描かれない。
前触れもなく表れて人間社会を打ちのめし、音もなく消えていく疫病。本当に病魔は消滅したのか。終結を祝う一方で、疑いと不安の気持ちが強く残っている。
市民の一人が吐き出すように言う。
「まったく、こいつが地震だったらね! がっと揺れ来りゃ、もう話は済んじまう……。死んだ者と生き残った者を勘定して、それで勝負はついちまうんでさ。ところが、この病気の畜生のやり口ときたら、そいつにかかわっていない者でも、胸のなかにそいつをかかえている」
人々は幾月もの間、しんぼう強く終結を待った。やがて「希望の風」が吹き、光が見え始めたとしても、病魔再発の兆候が現れたら「現状維持は続行され、各種の措置は強化される」ということを皆、心の奥で危惧しているのである。
多少の生活上の不足にも人間はすぐに「慣れる」。死ぬかもしれないという状況に慣れると、どんな危険も恐怖にも鈍感になる。
この「慣れる」ことと、最悪時の「記憶を忘れる」こと。それが悲惨であればあるほど、過去の災禍を「忘れる」。
カミュは、そのことを責めもせず、説教もしない。
市民が以前と少しも変わらず同じであること。それが彼らの強さ、彼らの罪の無さであり、そして、あらゆる苦悩、苦難、大きすぎる犠牲、喪失…を超えて、皮肉にもその事態に「慣れる」ことも、その時の「記憶を忘れる」ことも、困難を克服して生き続けていかねばならない人間にとっての「生きる力」ともなる。
しかし、カミュはこのような人間愛に満ちた想いを込めて、この一書を終わらせるわけではない。最後に、人類が未来永劫に繰り返すであろう、疫病との闘いを予言して、預言として、次の文章を遺している。(冒頭に掲載してある箇所を、再度紹介する)
「ペスト菌は決して死ぬことも消滅することもないものであり、数十年の間、家具や下着類のなかに眠りつつ生存することができ、部屋や穴倉やトランクやハンカチや反故のなかに、しんぼう強く待ち続けていて、そしておそらくはいつか、人間に不幸と教訓をもたらすために、ペストが再びその鼠どもを呼び覚まし、どこかの幸福な都市に彼らを死なせに差し向ける日が来るであろうということを」

ぺストという病
14世紀に起ったペストは黒死病とも呼ばれるが、流行した地域はヨーロッパ、中東、中国などの当時の文明諸国全体に及び、死者数は世界人口の3分の1に当たる7千万に達したと推測され、まさに人類絶滅の危機に瀕した事態であった。流行の発端は中央アジアの草原地帯というのが有力な説である。
ペストはもともと鼠の病気で、その在域地域の一つが中央アジアの草原地帯であった。モンゴル帝国によってヨーロッパに繋がる道が開け、1330年ごろからモンゴル帝国内で蔓延したペストは、1347年に黒海沿岸の町に到達。ジェノバの商人の船内で、ネズミを吸血したノミによってヨーロッパに持ち込まれた。
このノミが人間を刺して広がるという感染ルートは、ヨーロッパ上陸後は患者から空気を介して直接感染することになった。
ペスト菌はリンパ節で増殖し、肺に侵入、重症の肺炎を引き起こす。この状態の患者は咳やクシャミの際に、空気中に大量のペスト菌を輩出する。肺ペストの患者はほぼ100%死亡するために、空気感染の拡大とともに、膨大な死亡者が生じる。
カミュは、ペストに捕まった人の初期症状から、死に絶えるまでの患者の症状について克明に描写している。それは、現在報道される状況に酷似していて、新型ウイルスと肺ペストは同じものなのかと疑うほどである。
ペスト医師の風体

中世で、医師の診察を受けられるのはごく一部の人であり、医師もこの病で多くが命を落とした。患者数に対して医師の絶対数が不足していた。生き残った医師にしても、感染を恐れて診察を拒否した。たとえ診察を受けたとしても、膨張したリンパ節の切開や瀉血(血を抜く処置)程度であった。
ペスト患者の診察をするときの医師の風体は、全身を皮のマントで包み、顔には鳥を彷彿とさせる覆面をつけ、鼻の部分は尖っている。その中には香りの強い薬草が入っていた。
目は、今日のサングラスのようなものをかけ、患者と目を合わさないようにするためであった。何故なら当時は、患者と目を合わせるだけでも感染すると言われた。医師と患者は数メートル離れて診察にあたった。
また当時はこの感染症の原因が全く分かっていなかったので、診察は神に祈るのことと大差なかった。イタリアの役所からは次のような文書が発せられた。
「すべてのペスト患者は町はずれの原野に移され、人間の看護の手を離れて神の手に委ねられることになる」
これは患者を遺棄することであるが、今日でも、感染症対策としては基本的なことで、こういう隔離処置は各地で行われ、沈静化していったという。
その後の世界歴史の中でも。ペストは何回か大流行を起こしている。1664年のロンドンでは7万人が死亡。1720年、フランスのマルセイユでは4万人が死亡。19世紀末の中国、インドの場合は1000万人近くが死亡した。(「新疫病流行記」濱田篤郎)
現在のコロナ騒動との類似点を知るために

読み進むうちに、カミュは70年以上も前に、現在の世界的コロナ騒動を予測して描いているかと錯覚するほど、オランの町の状況と登場人物の世相がぴったり符合して不気味であった。
そして、どれほど過酷な厄災であれ、人間はそれを乗り越えていく力がある生き物であること。そういう根源的なことを、淡々と、けっして人間を批判するのではなく、誠実にその在り様を書き残しているのである。
ぜひとも、この機会に一読することをお勧めしたい本である。
【参考文献】
電子書籍『ペスト』アルベール・カミュ(宮崎峰雄訳、2017年新潮社)
『新疫病流行記』(濱田篤郎、2010バジリコ株式会社)