
1986年4月26日、ウクライナ北部の街、チェルノブイリ。ここで史上最悪の原発事故が起こりました。
大量の放射線物質が大気中に飛散し、放射線物質は風に乗って隣国のベラルーシの空を覆った「チェルノブイリ原発事故」事故からしばらくが経過した頃、ベラルーシの子供達に異常が見られるようになります。
放射線物質により喉に腫瘍ができたのです。甲状腺ガンでした。400人以上の子供が甲状腺ガンと診断され、すぐに手術が施されましたが、旧式の手術だったため、子供たちの喉には一生消えない大きな切開の跡が残ってしまいました。
その時、遠く離れた日本から一人の医師が駆けつけます。「菅谷昭(すげのや あきら)」日本有数の腕を持つ医師で日本での大学助教授の立場を捨ててまで現地に飛んだ日本人でした。
菅谷は人類史上最悪の事故に立ち向かうため、すべてを投げ捨てたのです。1956(昭和31)年、菅谷の父「菅谷保之」は長野県の更埴市で三代続く町医者をしていました。
懐中電灯一つで、厳しい雪山の峠を越え、患者のもとへ駆けつける熱心な医師でした口癖は「医者は24時間年中無休」。菅谷昭はその保之の5男でした。幼い頃はほとんど遊んでもらえることはなかったと言います。
父親の印象と言えば、大きな診察鞄と大きな背中。家に帰ってくればすぐに次の患者のもとへ行く――そんな毎日だったと言います。
1986年、日本の医療業界は世界でも最先端でした。日本中に高度医療機関が作られ、優秀な医師も増えていました。そんな中、信州大学医学部の第二外科に全国でも評判のチームがありました。
そのチームの専門は甲状腺ガンです。血管が集中する喉に腫瘍ができる甲状腺ガンはのどを大きく切開する必要があり、その傷跡が残ることが課題でした。
そして、信州大学のチームは、傷が残らない手術を研究していました。その中心にいたのが菅谷昭でした。菅谷の信念は、患者の後の人生も考えた手術をすることでした。
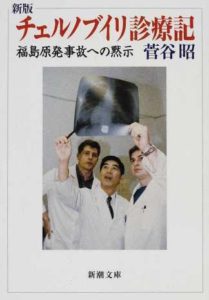
そんな中、当時のソビエト連邦でチェルノヴィリ原発事故が発生します。飛散した放射線物質の量は広島の原子爆弾の約500倍。史上最悪の事故でした。
しかもその頃は冷戦の時代だったため、事故の詳細はひた隠しにされていました。事故から5年が経過した1991年1月、菅谷は出世街道をひた走っていました。助教授になり、論文作成、後輩の指導と多忙を極めていた頃、自分が望んでいた医者の姿ではない事を感じていました。
ある日、テレビを見ていた菅谷は日本のボランチイア団体がチェルノヴィリ周辺で白血病の調査を行っている事を知ります。菅谷は白血病があるということは甲状腺ガンも存在する事を確信します。迷わずボランチイア団体に連絡し協力を申し出ます。
そして大学には2週間の休暇を届け、べラルーシに飛んだのです。現地の病院に着いた菅谷は病院の廊下に溢れる甲状腺ガンの患者を見て愕然とします。患者の多くは子供だったのです。
甲状腺の活動が活発な子供は放射線物質の影響を受けやすく甲状腺ガンになりやすい傾向があります。当時ベラルーシの子供たちの甲状腺ガン発生率は日本の40倍・・・。
さらに手術を受けた子供の首には耳元から喉を大きく切り開いた跡が残っていました。これを見た菅谷はことの重大性を認識し、自分がどうにかしなければと思ったと言います。
しかし、ボランチイアで訪れている菅谷には手術はできませんでした。次々と手術を受ける子供たちを前になす術がなかったのです。帰国した菅谷は、助教授としての仕事を多く抱え、より多忙になっていました。
ある日、妻の紘子にこう告げます。「25年勤めて来た大学を辞めて、ベラルーシで働く」。小児科医でもある妻の紘子は夫の性分を理解していたため「いってらっしゃい」と返したと言います。
1996年1月、菅谷はベラルーシのミンクスという町の小さなアパートに引っ越します。生活費は退職金を頼る生活でした。菅谷はすぐに国立ガンセンターに向かいます。そして院長に無給で雇ってもらいます。
異国の地でのたった一人の戦いの始まりです。1996年2月、菅谷は助手として手術に立会います。患者は14歳の少女でした。手術が始まる直前、少女は泣き声を堪えながら涙をながしていました。執刀医は少女の首にメスを入れ、大きな傷を負うことになりました。それを目の前にして何もできない自分自身に対し、怒りに震えていました。
さらに一ヶ月後、菅谷に執刀許可が下ります。菅谷は行動で見せると誓い、手術を始めます。当時の所長がお手並み拝見と菅谷の手術を見学にきていました。菅谷の手術は正確で迅速でした。そして驚くべき事に、切開した跡がほとんど残っていないことに現地の医師たちは驚きました。
ある日、新たな患者が病院を訪れます。名前はカーチャ。14歳。最も放射線被害が酷かった町の出身です。当時五歳だったカーチャは家の前で遊んでいる時に被爆しました。
カーチャはすでに手術を受けた他の子供達の前の傷を見て、震えていたと言います。そんな中、菅谷はいつも笑顔で話しかけていました。手術を終えたカーチャはほとんどわからない傷跡を見て驚きました。
ベラルーシの医師たちは菅谷の笑顔、技術、患者を思う気持ちに心を打たれていました。ある夜、菅谷のアパートに現地の若手の医師3人が菅谷の技術を教えてほしいと訪れます。
菅谷は自分の論文、手術のビデオ、あらゆる手を使って彼らに技術を伝えました。そうして若手医師を中心にベラルーシの医師たちは団結していきます。
1998年、ベラルーシに来て2年が経過した頃、菅谷は最も汚染が酷かった町で医師として活動することを決めます。そうしてその町の病院で再度無給で働き始めます。
その頃、ベラルーシの国中で菅谷の名前は知れ渡っていました。菅谷は手術の技術を教えたりする合間に、自分が執刀した患者の家を回りました。
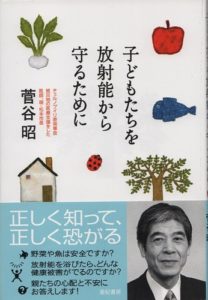
この時に思い描いていたのは父である保之の姿でした。大学の退職金を切り崩し、診察料も受け取らず毎日毎日出かけました。
菅谷は、ベラルーシで甲状腺ガンの手術を受けた全ての人の家を往診する事を決意します。
ある日、自身が執刀した患者が、子供を生む事を悩んでいました。菅谷は自分が全力でサポートするからと伝え、彼女を励まします。
菅谷はのちに被爆した人達が、このような事で悩みを抱えている事を知り、とても辛かったと振り返っています。
その後、元気に生まれた赤ちゃんを見て菅谷は涙して喜んだと言います。そして菅谷はおじいちゃんと呼ばれるようになります。
ベラルーシに来て6年、菅谷は医療技術も往診も若い医師ですべてできるようになったことを見届け帰国します。
今ではベラルーシで医師を志す者は必ず菅谷の話を学びます。
「ある日突然日本からベラルーシにやってきて、何も求めることなくひたむきに患者のために働いた男がいる」
ベラルーシの人達は尊敬を込めて菅谷を「センセイ」と呼んでいます。
2017年現在、長野県松本市の市長を務めながら、今でも1年に1度はベラルーシを訪れ、菅谷自身が往診をしています。自分が担当した子供たちが大人になり、子供を抱く姿を見ることが楽しみだと言います。
(編注=菅谷氏は2004年から2020年3月まで4期、松本市長を務めた)





