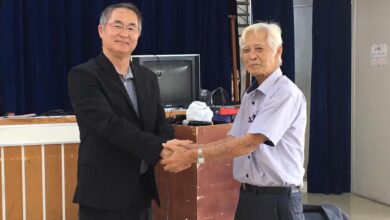先駆けだが短命だった週刊『南米』、移民を搾取する移民会社への批判や反官気運を一手に背負って戦った『日伯新聞』、移民会社の機関紙的役割を担って日本政府寄りの立場から「移民は永住すべし」と唱えた『伯剌西爾時報』 、数年間の出稼ぎのつもりで渡伯している大半の移民の叙情的な気分をくんだ立場から開戦前には海南島転住論まで説くようになった『聖州新報』の順で生起した。
お互いの読者層を代弁する形で激しく論戦を交えつつも、全体として祖国の軍国主義にまきこまれていき、読者はブラジルでも勃興したナショナリズム(国民意識の高揚)との狭間に立たされた。
ブラジル一般社会で黄禍論が高まり、第2次大戦に向けてブラジルの国粋主義が高揚して枢軸国移民に対する迫害が強まるという不穏な情勢を受けて、日本移民は精神的な足場を日本の国家主義に求め、日本語メディアや在外公館の指導をむさぼるように聞き入れた。
日本の国粋思想は基本的に領土という枠組みの中を想定された想念だったが、ブラジルという領土外で同じ考え方を持つことは、日本移民を受け入れたホスト社会にとって望ましいことではなかった。
それゆえ、2つのナショナリズムの対立が少数民族(エスニック)の迫害という形になり、第2次世界大戦までの大きな流れとなっていった。
■各論■
(1)新聞創刊の背景(黎明期1908~1925年)
一般にブラジル初の邦字紙といえば1916(大正5)年に発行開始された星名謙一郎の週刊『南米』といわれる。だが、実は1908年4月に神戸港を出港した第1回移民船「笠戸丸」の中で、香山六郎(こうやまろくろう)が謄写版の『航海新聞』を3号まで刊行していた。
週刊『南米』も謄写版であり、香山は大阪朝日新聞ブラジル通信員だったことを思えば、最初の〝移民新聞〟といえなくもない。
香山の父・俊久は細川藩士の末裔で、父の代に平民となり、熊本市で「不知火新聞」を創刊した人物。本人も1898年、12歳の頃、九州日日新聞の活字工をした経験がある。1904年に日露戦争が始まり、海軍兵学校を受けるも不合格となり、文学書を読みあさるようになる。
その後、上京し、日本大学予科(植民科)に入学し、遠藤清子ら発行の学生雑誌社の下回り記者として平塚雷鳥、与謝野晶子、大町桂月、徳富蘇峰、堺枯川、幸徳秋水らと会う。来伯当時22歳、徴兵逃れのためのもあって、叔父・土屋員安(つちやかずやす)の勧めで南米移住を決意した。
明治中期以降、日本では各地に新聞が生まれ、言論の自由、西洋に学ぶ気運が強く、「日本人」という国民意識を形成していた時代だ。日本は日清・日露戦争の勝利の美酒によっていた。
後に水野龍(りょう)と運命の出会いをし、日本移民の実験台として渡伯することになる鈴木貞次郎(南樹)もまた、1905(明治38)年頃、故郷にある山形新聞で数年間ほど記者をしていた 。東京にも計7年ほど住んでいたとある。(敬称略、つづく、深沢正雪記者)