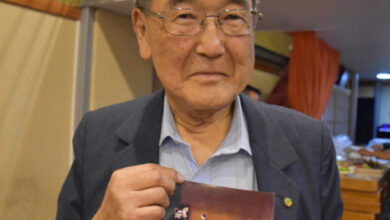ネーネーズによる「十九の春」(https://youtu.be/3UrbyTgRlu8)
1月15日付本紙に掲載された醍醐麻沙夫氏の「まぼろしの『十九の春』」を大変興味深く読ませて頂いた。「ラッパ節」との関係において「十九の春」の源流を問い、その元歌が「与論ラッパ節」であり「十九の春」までの「中間的な歌」として明らかにしています。
そして日本全国で流行っていた「ラッパ節」が第1回ブラジル日本移民を乗せた笠戸丸でも盛んに歌われ船上の沖縄県人移民にも影響を与えたのではないか、「つまり私が言いたいのは、かなりの日数をかけて沖縄に伝わったラッパ節ですが、笠戸丸船上ではいきなり出会ってしまったという面白さです」と醍醐氏は述べています。
そして「笠戸丸がサントスに着くころには、沖縄本島でラッパ節が『十九の春』に変身したような変化がすでに起きていたのではないかと推察されるのです」、とも述べています。
そこまで読んで私は、「それはチョッと歴史的に飛躍し過ぎるなー」と感じ、また「笠戸丸移民のコロノ(コーヒー園労働者)の長屋からすでに『十九の春』に似た歌い方と三線の音が漏れていたかも、というのが私の空想です」、という空想(想像)の在り方に疑問を抱いて筆を執っている次第です。
醍醐氏の「十九の春」への愛着の念が強く伝わってくるけれど、ここで私の意見を述べてみたいと思います。
「十九の春」の元歌は「与論小唄」
さて、戦後沖縄で生まれた「十九の春」(本竹裕助補詞・編曲)の元歌は、「ラッパ節」が深い影響を与えて与論島(よろんじま)に生まれた「与論小唄」である、と言われている。その歌詞を対比してみましょう。
十九の春
1 私があなたに ほれたのは
丁度十九の 春でした
いまさら離縁と 云うならば
もとの十九に しておくれ
2 もとの十九に するならば
庭の枯れ木を 見てごらん
枯れ木に華が 咲いたなら
十九にするのも やすけれど
4 一銭二銭の 葉書さえ
千里万里と 旅をする
同じコザ市に 住みながら
逢えぬ我が身の せつなさよ
6 奥山住いの ウグイスは
梅の小枝で 昼寝して
春が来るような 夢をみて
ホケキョホケキョと 鳴いている
(3番と5番略)
与論小唄
1 私が貴方にきた時は
丁度十八花ざかり
今さら離縁というなれば
もとの十八なしておくれ
2 十八なすことやすけれど
枯れ木に花が咲くものか
枯れ木に花が咲くなれば
もとの十八なしてやる
4 七円一枚のハガキさえ
世界国中旅をする
貴方と私はままならぬ
障子一枚で籠の鳥
6 奥山住いのウグイスが
梅の小枝で昼寝して
花の散るような夢を見て
ホーケキョホケキョと泣いている
(3番と5番略)
このように見てみると、「与論小唄」が「十九の春」の元歌であることは自ずと明かでしょう。ところでこの「与論小唄」もまた与論島に流行った「与論ラッパ節」が前提となって生まれたと言われている(参照 仲宗根幸市編著『琉球列島島唄紀行』第一集)。
はやり唄「ラッパ節」と「与論ラッパ節」
1898年(明治31年)8月に与論島は、全戸崩壊という大きな台風に襲われ甚大な被害を受け、明日の食事にも窮する困窮と悪疫の流行にみまわれた。その翌年から数次にわたって千数百の大人たちが職を求めて長崎県口之津に石炭運搬労働者として集団移住、いわゆる出稼ぎ労働者となった。
当時の日本のエネルギー資源は石炭が中心であり、官営の三池炭鉱が三井物産の手に移り、石炭産業の隆盛を極め、全国から多くの労働者が寄り集まっていた。
しかし、与論の出稼ぎ労働者たちは劣悪な労働条件・重労働の上に賃金は本土労働者の半額という差別を受けていた。
「働けど働けど一向に借金の減らない与論の人たちの不満は高まり、加えて生活風俗の異なる与論の人たちへの人種偏見と差別はひどく、彼らは与論長屋に固まって『ヨーロン』と蔑まれていた。改善されぬ労働条件、本土ヤマトゥンチューによる差別への苦悩、希望を見出し得ぬいらだち…、出るのは愚痴と溜息ばかりであった。その時、彼らを慰めたのは、はやり唄の『ラッパ節』であった」のである(仲宗根幸市著『「しまうた」を追いかけて』312頁)。
ラッパ節は、1904年(明治37年)日露戦争の頃に演歌師添田唖蝉坊によって七五調4連の歌詞で流行り唄として誕生し、忽ち日本人の心を捉えて全国に広がり、九州の炭鉱労働者の街をも風靡した。
その普及は、「月が出た出た」でお馴染みのあの「炭坑節」に代表されている。与論長屋の人々もまたラッパ節に心を奪われ、与論三線の音色に乗せて日々の苦しい思いや悲しみを癒した。
やがて島に帰った口之津の与論長屋の人々は、帰郷後もラッパ節を三線に乗せて歌い続けた。そして幾つもの「与論ラッパ節」が生まれたのである。それは、大正の終わり頃から昭和初期の頃(1925-6年から1930年代初め頃)と言われており、ラッパ節誕生から20余年の歳月を経て与論島に土着化した与論島独特のラッパ節である。
はやり唄としてのラッパ節がやがてその生命力を失い消えていった後も「与論ラッパ節」は与論の人々に愛され歌い継がれた。このような歴史的経緯の中で、上記歌詞の与論島のしまうた「与論小唄」が生まれ歌われてきたのである。
「十九の春」の誕生

さて、「与論小唄」がどのような経緯を辿って沖縄に伝播し、「十九の春」の元歌となったのだろうか。
そもそも奄美列島の与論島は、琉球弧の島嶼の1つであり、1609年の薩摩侵略までは琉球王国の領地で交流は盛んであったが、その後薩摩の直轄地とされ薩摩支配下に置かれた。交流は大きく断絶した。
しかし、王国が廃絶された後の明治時代も大正・昭和の時代も沖縄諸島の人々との行き来や文化的交流は行われてきた。だから与論島に根づいた与論ラッパ節や与論小唄も当然沖縄本島、宮古・八重山の与那国島まで長い時間を掛けて伝播していた。
第2次大戦前には那覇の遊郭辻町で「尾類小(じゅりぐゎ)小唄」(「じゅりぐぁ」は沖縄語、娼婦のこと)として歌われ流行したことが伝えられている。
また北部今帰仁村運天港に出入りした与論の人々が歌っていたという言い伝えもあるし、八重山西表島の炭鉱に九州の人々が就労し歌っていたとも言われている(上記仲宗根幸市著書参照)。
特に太平洋戦争において日本が敗北し、沖縄列島並びに北緯28度線以南の奄美諸島・小笠原諸島をアメリカ占領軍の支配下においた時期(1945年―1954年12月に奄美・小笠原諸島が日本に復帰されるまで)には奄美諸島の人々との交流は、米軍基地への就労者や基地周辺の歓楽街に働く人々も増え、与論島の人々との交流も盛んであった。
コザ市の歓楽街吉原には「与論小唄」を元歌にした替え歌「吉原小唄」が流行し「与論ラッパ節」も歌われていたのである。
このような歴史的経緯・背景の中から1972年に与那国島出身の本竹裕助氏補詞・編曲の「十九の春」が発表された。それは、日本語(標準語)による七五調歌詞の新民謡と言われる歌である。
そして同74年に沖縄を訪れた田端義夫がこの歌に感動し、翌年「島育ち/十九の春」を発表、大ヒットして全国に広く伝播した。このことは良く知られていることである。
笠戸丸沖縄県人移民の頃は琉歌――八八八六調

ところで、上記のような「十九の春」の歴史的経緯・背景を考えると、笠戸丸船上で盛んに「ラッパ節」が歌われ沖縄移民に影響を与え、「笠戸丸移民のコロノの長屋からすでに『十九の春』に似た歌い方と三線の音が漏れていたかも…」と捉えるのは、果たして的を得ているであろうか。
ラッパ節は、笠戸丸移民時代の沖縄にはまだ伝播しているとは言い難い状況であったであろう。それが社会的に伝播し始めたのは大正の終わり頃から昭和初期以降のことと云われている。醍醐氏には失礼だが、上記の文面は時代的考証抜きの飛躍した論述になってはいないだろうか。
香山六郎氏は、その著書『回顧録』の「第7章笠戸丸」において、「その夜、沖縄移民の船室で沖縄哀調の唄が唄われ、蛇皮線の音が流れ、他の移民の旅心をそそった。私は高桑君と夜の更けるまで聞き入った。沖縄の哀調芸術を語り、『三味線ではあれだけの原始的哀調は得られないね』と言ったりした」(122頁)と沖縄三線(蛇皮線)の真に迫るようなことを書き記している。
船上の沖縄移民たちは、三線の「原始的哀調」の音色を響かせ何を歌って香山の胸に感動を与えたのだろうか。
日本・沖縄県人移民100周年記念祭典に際し、「海を渡った100年の三線」として話題を呼んだ読谷村出身の宮城伊八(みやしろいはち)三線(その4男宮城清進氏保存)や保存はされていないが持参していた北谷村(ちゃたんそん)出身の金城太次(かなしろたいじ)も船上で三線を奏でた1人であろう。
彼らが青春を生きた19世紀後半から20世紀初頭の頃の沖縄の社会的・文化的環境を考えると、彼らが「原始的哀調」の音色を響かせて歌った歌は、恐らく八八八六調の沖縄語の琉歌(日本の和歌とは異なる琉球に独特な形式の沖縄語の短歌)であったに違いない。
1879年に明治=日本政府によって琉球王国が廃絶され、多くの首里士族らが碌を失い地方に下野し農民となって生活した。下野した彼ら(良人=ゆかっちゅと呼ばれた)は、農民から農業を学びながら琉球王国時代の歴史の中で培われ琉歌の普及や農民が口伝で歌い続けてきた古謡・労働歌や童歌を「村芝居」の踊りの歌詞に取り入れ普及する役割を果たしていた。宮城伊八や金城太次もその影響を受けていたであろう。
笠戸丸沖縄移民が船上で三線に乗せて歌った歌は、残念ながら何も残されていない。察するに例えば、
◎恩納ナビの「恩納松下に禁止ぬ碑ぬ立す恋偲ぶまでぃぬ禁止やねさめ」(恩納村の松並木の下に禁止札が立っているが恋をすることまで禁止する立ち札ではないだろう)
◎吉屋チルの「恨む比謝橋や情けねん人ぬわが身渡さとぅ思てぃ架けてぃ置きやら」(恨む比謝橋は情けのない人が私を(遊郭)に渡そうと思って架けたのでしょうか)
などの琉歌や谷茶メー、国頭サバクイなどの労働歌、童歌等々、八八八六調の沖縄語の歌曲ではなかったか、と思うのである。
そもそも笠戸丸移民の頃の沖縄の人々の日常の言語は、沖縄語・ウチナーグチが中心であり、明治政府が方言取締り令・方言札で禁止を強めても生活の中から方言はなくならなかった。だから笠戸丸船上で歌われた日本語歌詞の七五調のラッパ節は、沖縄移民の心を捉えるには至らなかったであろう。
醍醐氏は、「笠戸丸移民のコロノの長屋からすでに『十九の春』に似た歌い方と三線の音が漏れていたかも…」と書き、かつまたそれを「私の空想」ともお書きになり、「その歌を聞いてみたいと思うのは私だけでしょうか」と問うている。
だが、その時代の諸条件・背景を考証するならば、そのように問うのは歴史のロマンとしては面白いけれど、やはり単なる「空想」になり終わっているように思えてならないのである。(2021年1月25日)