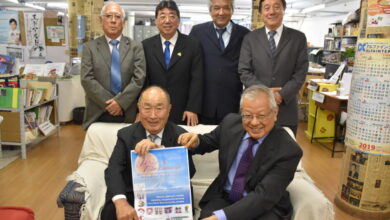安慶名栄子著『篤成』(16)
楽しいこともありましたし、仕事も順調にいっていたのですが、父の心にわだかまりが残っていました。日本に残されていた2人の兄たちのことが気がかりで父は昼夜兄たちの事を考えていたのです。
兄たちは、当時太平洋戦争の最中にアメリカ軍に攻撃され始めていた沖縄で学校に通っていたので、その事が父にとって一番の不安だったのです。なぜなら、知っている限りでは、男女を問わず、学生は全員国を守るようにと学徒隊として徴兵されていたとのことです。
父は心の奥では最悪の事態を恐れていました。さらにひどい事に幾日か過ぎてから、兄たちが戦死したとの噂が広がっていたのです。
父は信じませんでした。私はといえば、信じないふりをしました。
実際には父の苦痛は日増しに大きくなるばかりで、子供の私たちには何一つ力になれませんでした。父のためになることはただ一つ、愛してあげることだけでした。
どんなに辛いことがあっても、父は一日として、日本に戻って二人の兄たちと一緒に暮らす夢を忘れることはありませんでした。だから私たちにも日本語を勉強させました。私は日本語の教材を丸め、大きな風呂敷に包み込み、腰に巻いてスカートで覆って誰にも見られないようにユーカリの森の中を通り抜けて日本語を学びに行きました。
ばれたら先生が逮捕される恐れがあったのです。本当に怖かった。
1945年8月に日本の広島と長崎に原子爆弾が投下されましたが、私たちの家族にも爆弾が落ちました。紙の形をした爆裂弾でしたが、私たちには頭上に鉄を落とされたかのように痛み、熱い油で焼けるような感じがしたのです。
沖縄の叔父から手紙が届き、内容には篤政と信綱の戦死が確認されたのであります。
「うそだ!」「うそだ!」、父は大声をあげて泣いた。ずっと「いやだ、嘘だ!」と叫びながら父の頬には大粒の涙が流れ続けていました。
私たちにはどうしようもなく、父の足に縋り付いて一緒に泣きました。胸が引き裂かれるような痛みを感じていた父と同じ痛みを私たちは感じていました。兄妹全員が父の足に縋り付いてただ泣き叫ぶのでした。
手紙を届けてくれたのは、政孝叔父さんでした。叔父も私たちと一緒に子供のように泣きました。奥さんと子供を一挙に亡くしていた叔父は私たちの痛みを痛切に感じていたのです。政孝叔父さんには父の痛みがよくわかり、同じ傷を負ったもの同士の、同じ苦痛に直面したもの同士の無言の哀れみが通じていました。叔父の心の傷は治りかかっていたが、父の心の傷からはまだ血が流れていました。
その上、叔父は、最初から私たちと道程を共にしており、最初から私たちの苦痛の道を知っていました。よく知っていたのです。
常にまた逢う日を夢見て、沖縄で再び一緒に暮らす計画を立てていた父にとって2人の子供を亡くしてしまった痛みがどれほど大きかったか。6歳から7歳になりかかっていた私でも察したのです。
その時からでした。私は父を幸せにしたいと思いました。