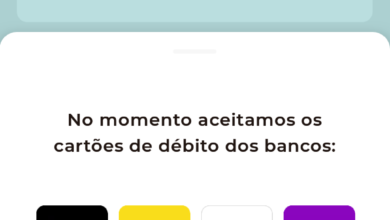コロナ禍で、互いの「繫がり」を切らないように助け合う知恵を交換するネットワークが急速に普及し、大きな助け合いとなっている。
しかし、少し時代を遡れば、病気や災害による相互扶助の手段は、限定的、限域的なことであった。「近代医療・医薬」が堰を切ったように始められたのは1950年代からだと言われている。
日本の国民病とも言われた結核のような疫病の場合は、医療も薬も情報も十分病床に届けられることはなく、むしろ本人も家族も外部に知られないように隔離生活の中で生きることを強いられた。
一般的に、一旦病気になると外部との接触を避け、ひたすら病と向き合う闘病生活より他になかったのである。
しかし、そのような苛酷な病との戦いの日々から、文豪たちは多くの優れた文学作品を世に送ったのであった。その一部を病名とともに復読する。
結核
結核は太古の昔からその正体を知られないままに、人類の起原とほとんど同じくして見られたものらしい。その病跡を残したミイラが新石器時代や、紀元前1000年前のエジプト第21王朝の墓から発見されている。
この病はわずか150年前、1882年、ドイツ人医師・コッホが結核菌を発見するまで、遺伝であるとの伝説が尤もらしく広がり、患者を抱えた家族は悲惨な運命をたどった。患者は、日に日に両肺を蝕ばまれ、消耗し、痩せこけて死に至った。
そして、欧米、日本でも産業革命の劇的な社会変化とともに、地方から集められた工業労働者に蔓延した。1900(明治33)年7万人を超えた統計上の結核による死亡者数は、1930(昭和5)年12万人、1940(昭和15)年には15万人を超えた。
死亡者の圧倒的多数は、繊維産業を支えた10代の少女たちであった。1925年(大正14年)、改造社より刊行された細井和喜蔵のルポルタージュ『女工哀史』は、著者自らの紡績職工としての体験と見聞を交えて描かれた。
『あゝ野麦峠』、副題「ある製糸工女哀史」(山本茂実、1968年ノンフィクション文学)から、労働条件の過酷さが痛ましい。
当時、結核が感染症であり死に至る病であることは樋口一葉や石川啄木の短い生涯からも知ることができるが、たとえば、この病への社会的偏見は厳しく、農村では納屋に隔離したり、都会でもその家の前をハンカチを鼻と口にあて、息をせず急いで通り抜けるというような風潮が一般的であった。伝染病の障害者となった場合の介護は、ごく限られた身内や友人の手に委ねられた。
歌人 正岡 子規(1867年―1902年)

その35年の生涯の後半生は、まさに結核との闘いであった。彼は23歳のとき、結核により喀血した。子規と号したのも、血を吐いて死ぬ時鳥に我が身をなぞらえてのことであるという。子規は明治28年に日清戦争に従軍し、帰路の船中で吐血した。
1901(明治34)年9月2日から書き始めた『病床六尺』には、その日の食事内容と飲んだ薬について書かれた。
薬は1900年当時、治療薬としてはクレオソートがかなり用いられていた。これは特異な刺激臭を持つ油で、強い防腐、殺菌、局所麻酔、虫歯に詰めて鎮痛に用いたりするもので、結核には効力はなかった。
服用すると、息がタール臭くなるが、当時の医師も患者もそれが、結核菌と戦っているように思えたのであろう。
子規の結核は脊椎を侵し、症状悪化に伴い、31歳のとき腰部の手術をうけたが好転せず、34歳の頃、人力車で外出したのを最後に臥床生活に入る。
徐々に進行していく疾病とそれによる患部の苦痛を併せもちながら、『病牀六尺』に象徴される狭い六尺(1.8メートル)の床の上での重度障害者としての生活を送ることになる。それを子規は次のように記述している。
「病床六尺、これが我世界である。しかもこの六尺の病床が余には広過ぎるのである。僅かに手を延ばして畳に触れる事はあるが、蒲団の外へまで足を延ばして体をくつろぐ事も出来ない。甚だしい時は極端の苦痛に苦しめられて五分も一寸も体の動けない事がある」
病状が日に日に悪化する状況は、「足あり、仁王の足の如し。足あり、他人の足の如し。足あり、大磐石の如し。僅かに指頭を以てこの脚頭に触るれば天地震動、草木号叫」
「たまらんたまらんどうしようどうしよう」と連呼し、「自殺熱はむらむらと起こってきた」「誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか、誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか」と絶叫する
家族と友人との障害者相互受容
母や妹は食事やトイレなど日常的な介助に献身し、漱石や虚子らは口述筆記して『墨汁一滴』や『病牀六尺』を新聞「日本」に連載した。多くの知人や弟子たちが、感染症である結核を危惧しながらも、珍しい土産物などを持参してたびたび見舞いに訪れている。
病床周辺も配慮された。伊藤左千夫により石炭ストーブがとりつけられ、高浜虚子の配慮により病室の障子をガラス戸にした。
特にガラス戸にしたことにより、庭とそこに咲く草花の世界が開けたのであり、自殺をも考えた苦痛から庭から見える草花の生命力や四季によるうつろいを凝視し、それが、病気を受け入れ精神を昇華していく一因となる。
『病床六尺』の最終回が新聞に載った日、1902(明治35)年9月18日の朝、「体すきなしという拷問を受けた。まことに話にならぬ苦しさ」と述べ、翌19日、脊椎カリエス結核との闘いを終え、永眠した。
子規は、病気による苦痛とそれによる障害を受容しながらも、死に至るまで意欲的に創作活動を続け、『墨汁一滴』『仰臥漫録』『病牀六尺』などの随筆を口述筆記などにより新聞に発表し、また歌を詠み(『子規歌集』)、さらに仰臥した状態で『草花帖』などの写生画も遺したのである。
樋口 一葉(1872年―1896年)

子規より6年早く、1896(明治29)年11月23日、24歳で樋口一葉が肺結核で世を去る。小説家としての活動は、わずか14カ月であった。11月27日付けの主治医三浦省軒からの領収書に炭酸クレオソートの記載がある。
代表作「たけくらべ」「にごりえ」「十三夜」。
堀 辰雄(1904年―1953年)

堀辰雄の『美しい村』は1933(昭和8)年の夏に軽井沢で書かれたが、その時出会った少女、矢野綾子はすでに肺結核に侵されていた。
「風立ちぬ、いざ生きめやも」は有名な詩句となって知られているが、堀辰雄自身も、喀血、入院、療養を繰り返しつつ、清冽な作品を世に送り続け、1953(昭和28)年5月28日、49年の一生を終えている。
代表作『風立ちぬ』『かげろふの日記』『大和路・信濃路』
芥川 龍之介(1892ー1927年)

1900年前後、海外に渡航する日本人は大きく2つに分けられた。一つは移民で日本郵船の太平洋航路は日本移民で溢れかえり、もう一つはヨーロッパへの留学生であった。
そして、第一次世界大戦後の1920年頃には欧米では海外旅行ブームが起き、日本人の中にもその傾向が見られたが、健康面で多くの問題があった。
芥川は1915年、東京大学英文学部に在学中に『羅生門』を発表し、文学界にデビューした。卒業後に大阪毎日新聞の嘱託記者として1921年3月、中国を旅行するが、体調はすこぶる悪く、上海の里見診療所に入院し、診断の結果、肺結核であることを宣告される。
新聞社からの催促もあり、体調不良の中、南京、抗州、蘇州、楊州、漢口、洛陽、北京、天津を訪問し、7月に帰国する。帰国後の過労は、心身両面を蝕み、帰国から6年後の1927年7月服毒自殺に至る。35歳であった。
その作品の多くは短編小説である。また、『芋粥』『藪の中』『地獄変』など、『今昔物語集』『宇治拾遺物語』といった古典から題材をとったものが多い。『蜘蛛の糸』『杜子春』といった児童向けの作品も書いている。
竹久 夢二(1884年―1934年)

画家で詩人の夢二は1931年5月、横浜から日本郵船の豪華客船・秩父丸でアメリカに渡航するが、サンフランシスコに到着してすぐに結核が再燃した。
ロスアンジェルスでの展覧会で得た収益で、ハンブルグ、パリ、スイス、オーストリアを経由して、ベルリンに半年滞在して、現地の美術学校などで日本画の講義などをするが、結核の症状は改善せず、帰国し、1934年9月、長野県信州富士見診療所で死去する。代表作『宵待ち草』
佐伯 祐三(1898年―1928年)とその娘の結核
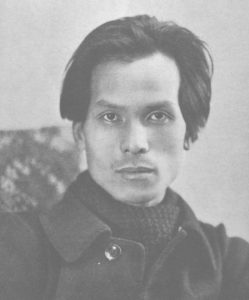
画家・佐伯祐三は芥川や竹久と同じように結核により30歳で死去した。1924年、初めてパリの土を踏む。6年足らずの短い活動期間の画家生活の大部分をパリのモンパルナス等で過ごした。
佐伯はパリに長く滞在することを望んでいたが、佐伯の健康を案じた家族らの説得に応じいったん日本へ帰国した。それから間もなく2度目の滞仏をはじめたが、佐伯はその後ふたたび日本の土を踏むことはなかった。
当時パリには300人を超える日本人画家が活動していたが、佐伯はそうした画家たちとの絵画談議には参加しなかった。それは彼自身が「結核」という病に侵され、あまり余命のないことを自覚していたからかもしれない。
佐伯は旺盛に制作を続けていたが、持病の結核が悪化したほか、精神面でも不安定となった。
自殺未遂を経て、セーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入院。一切の食事を拒み、妻に看取られることなく、最初の渡仏から4年後の1928年8月16日、衰弱死した。6歳の一人娘も、同年同月30日に結核で死亡した。
結核は、社会の欠陥が生む病気ともいわれ、過酷な労働、非衛生的な生活、栄養不足によって蔓延した。たしかに、ストレプトマイシン、イソニアジドの発明は結核の絶滅に貢献したが、今日でも年間数万人の患者数を出し続けている。
大自然、人体には、悪も毒も共存する
今回の疫病騒動で最も腑に落ちたのは、「自然のことは分からない。ウィルスの正体は掴めない」と言う言葉の意味であった。
「ウイルスvirus」の言葉の由来は「毒液」または「粘液」を意味するラテン語で、古代ギリシアの医師ヒポクラテス(紀元前460年ごろ – 370年ごろ)は、「病気を引き起こす毒」という意味でこの言葉を用いたと伝えられている。
すなわち、人間の体には、善も悪も、ウィルスも細菌もすべてが共生し、互いが無限に作用し合う。自然界には、一方を排除して片方だけで成立しないこと。全てが繋がり、連鎖し、共存関係にあることを再確認した。
むしろ、文豪たちの傑作が、疫病との闘いの中から生まれたことに、万感こもごも至るのである。
【参考文献】『薬の話』山崎幹雄 中央公論1991年