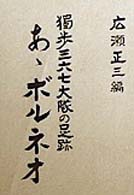《戦後移民60周年》=聖南開拓に殉じた元代議士 山崎釼二=『南十字星は偽らず』後日談=第6回=「仕事見つからず気の毒」=日本人形工場で住み込み
ニッケイ新聞 2013年2月7日

「とても気の毒でした。山崎さんは中々仕事が見つからなかったようです」。田形俊子さん(87、鳥取)=サンパウロ市ビラ・ブルデンテ在住=はそう述懐する。
出聖したとはいえ、山崎に頼れる知り合いは少なかった。二宮マツ(二宮正人弁護士の母)が田形さん宅に山崎を連れてきて「世話をしてくれないか」とお願いした。55年7月頃の話だ。数多くの仲人を務めたことで知られる二宮だけに顔が広く、そんな世話もしたようだ。
「山崎さんは『とにかくアマゾンは大変なところだった』と言われていました。随分お苦労されたようです」と田形は推測する。当時、田形宅はサンパウロ新聞社(移転前、トマス・デ・リマ街)の隣の四部屋もある家だった。山崎とアイン、讃南(本来はサンズイに南)、朱実の4人がその一部屋に仲良く住んだ。
「とても仲のいい家族でした。最初は3、4カ月という話だったんですが仕事が見つからず、結局一年ほどいましたよ」という。「アインさんはとても朗らかな方で、山崎さんも威張ったような感じはまったくなく、よくサーラで楽しく団欒していました」。
田形は言う。「すぐ向いに内山勝男編集長(サ紙)が住んでいて、奥さん(しずえ)と知り合いだったので、『山崎さんを雇ってあげたら』と勧めたんですよ。でもしずえさんは『夫は山崎さんを雇うなら、ちょっとした月給ではできない』と断ったと聞きました」との状態だった。「元代議士」という肩書きは職探しの重荷だった。
その後、山崎はイピランガ区で紙製の日本人形作りをする町工場で住み込みとして働いたが、数カ月で辞めた。意気揚揚と南米移住しアマゾン開拓へ、一転して脱耕、居候、町工場——忸怩たる思いが湧いてもおかしくはない。
山崎は56年中頃、サンジョアキン街のアパートを借りて妻子を住ませ、単身で聖南海岸部ペルイベに向かい、ドイツ人土地所有者から請け負った原始林の開拓を始めた。請負い料は高くなかったが、ボルネオ時代を彷彿とさせる開拓生活にようやく手が届いたとやりがいを感じた。

その一方で、妻子の元へは月に一度帰ってくるだけだった。アパートには三部屋あり、二部屋を下宿として貸出していた。その一つに入ったのが宮尾進(サンパウロ人文研元所長)だ。1年ほど下宿していたが、「山崎さんにはほとんど会ってないな」と振り返る。もう一つには坂和三郎(サンパウロ日伯援護協会副会長)と蒔田実(故人)が同居していた。坂和も「アインさんとは毎朝一緒だったからよく話をした。山崎さんの方はほとんど顔すら見ていない」という。
若きアインにとって夫のいない寂しい毎日の中で、数少ない慰めは同年代の蒔田や坂和と一緒にバイレに行くことだった。坂和は「アインさんとはよくカーザ・ポルトガルのバイレに行った。踊るのが好きな人だった」と懐かしそうに思い出す。
蒔田は坂和より5歳ほど年上だが同じ日大卒で、53年にアマゾン移住してすぐに出聖した経験があり、アインにとって特に親しみのわく存在だったようだ。
坂和は「アインさんはとてもキレイで明るい人だった。時々、思い出したようにボルネオが懐かしいと言っていた。日本にいるより、ここに居たほうが気持ちが安らいでいたのではないか」と推測した。(つづく、深沢正雪記者、敬称略)